#3 チャットアプリで起業も、LINEの登場でピボットの道へ。Minto(元クオン)水野氏が見出したキャラクタービジネスの可能性
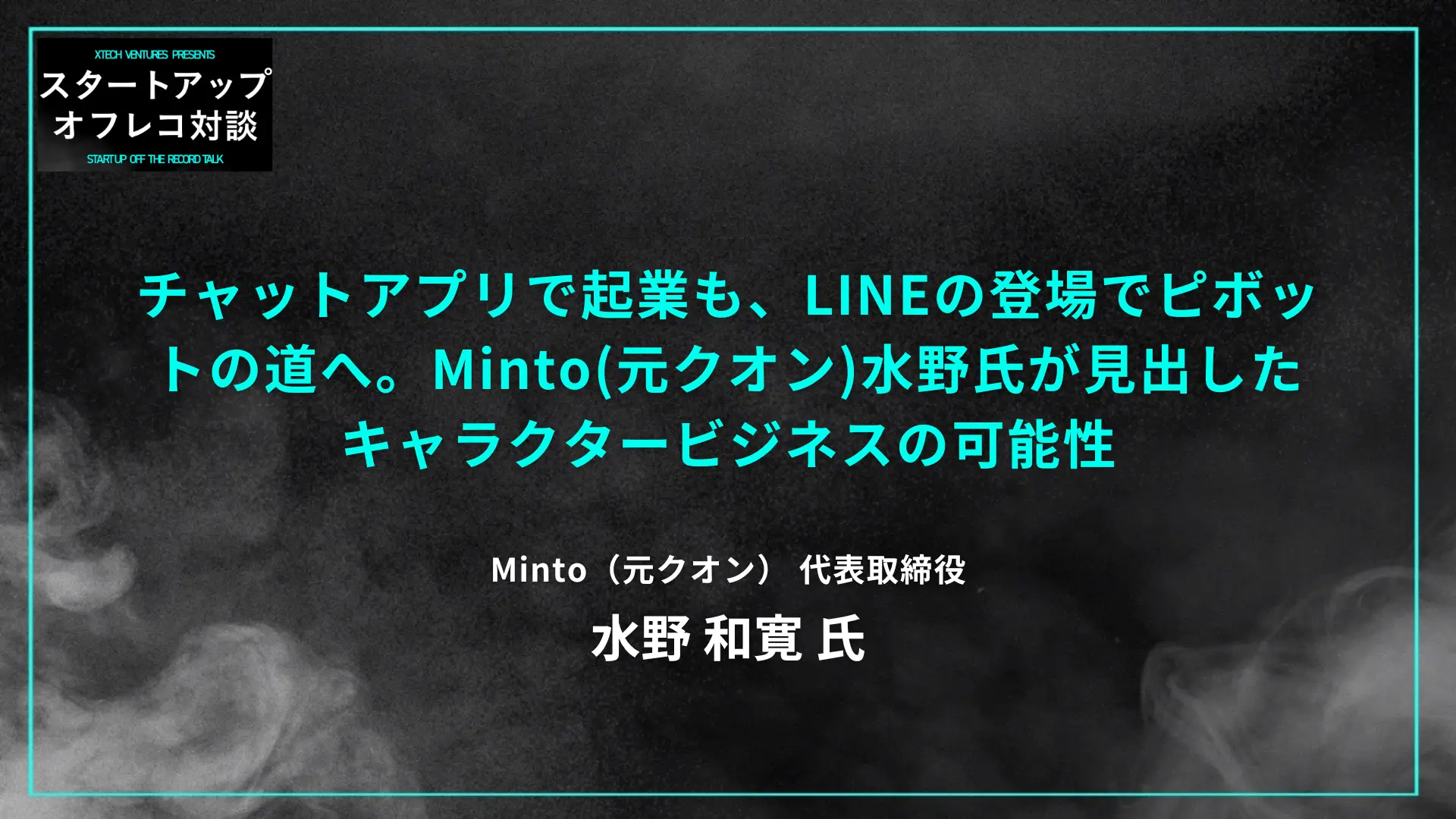
#3 チャットアプリで起業も、LINEの登場でピボットの道へ。Minto(元クオン)水野氏が見出したキャラクタービジネスの可能性
📕Summary
「スタートアップ オフレコ対談」は、XTech Venturesの代表手嶋とゲストの方をお呼びして対談する番組です。今回は日本をリードするクリエイターエコノミー企業、株式会社クオン代表の水野氏との"オフレコ"対談です。
クオンはキャラクターの開発、チャットプラットフォーマーへスタンプを提供しています。チャットアプリで起業するも、LINEの出現によってピボットを強いられたのち、どのようにスタンプのダウンロード数世界一を誇る事業に行き着いたのでしょうか。そして、後半はクオンとwwwaapの合併、「株式会社Minto」の設立の秘話をぶっちゃけていただいています。
🔊Speaker
・手嶋 浩己
Xアカウント [@tessy11])
XTech Ventures 代表パートナー
・水野 和寛 氏
Xアカウント[@mizunoq]
Minto(元クオン) 代表取締役
対談内容
※記事の内容は2021年10月時点のものです。
海外に行き、DTMにハマった水野氏の学生時代
手嶋:私と水野さんはざっくり、もう13年くらいの友達関係ですよね。同い年で、仕事で知り合いました。とはいえ、半分プライベート、半分仕事みたいな形で継続的にいろいろとやりとりをしている仲です。
まず「水野さんって何者なの?」と。大学から最初の就職までくらいを軽く話してもらえますか?
水野:法学部に入っていたんですけど、授業の単位をそんなに取らなくても良かったということもあって、1年目はひたすら東南アジアとかを旅行していました。元々、旅行が好きだったというのもありますし。大学に入って「自由だ!」という気分になっちゃって、東南アジアとかを旅行していたんです。
海外から戻ってきて、学校にも行きはじめて、そこからはまったのがDTMです。先ほどEDMという話が出ましたけど、DTM(デスクトップミュージック)です。DTMで、テクノとか、EDMとかを自分でつくっていて。その当時、いわゆるクラブミュージックみたいなものが流行りはじめたくらいでした。僕はクラブにはまるというよりは、どちらかというと家でひたすらパソコンを使って音楽をつくっていました。
今は当たり前ですけど、昔の音楽のジャンルで言うと、ダンスミュージックとかテクノとか、一気にグローバルに流通するジャンルだったので、それが面白いなと思って、自分で曲をつくって、ヨーロッパのレーベルとかに送ったりしてました。
あとはインターネットにはまっていたので、自分で掲示板をつくったり、サイトをつくったり。ちょっと世代が出ちゃいますが、そういうことを学生時代にずっとやっていて。
そんなことをしていたので、大学を1年、留年していたんですよね。4年で卒業できなくて。大学5年生のときに、そうは言いながらも就活はしないといけないなと思って、就活をしはじめるんですけど、何をやろうかなと思って、その当時、読んでいた『デスクトップミュージックマガジン』というコンピュータの雑誌のちっちゃい出版社・寺島情報企画というところがあったんですけど。
自分も音楽をつくるときにこの本を読んでいるし、ここで働かせてもらいたいなと思って、アルバイトに応募して。だから、大学5年生のときにアルバイトで入って、そのまま寺島情報企画に入社しました。
寺島情報企画へ就職/デコメ・アプリ事業立ち上げ
手嶋:なるほど。それが2000年くらいですかね?
水野:それくらいですね。
手嶋:リスナーの人たちは「寺島情報企画って何?」って感じだと思うんですけど。当時のモバイル業界では超有名会社ですよね。今も存在するんですけど。一番勢いがあったのは、フィーチャーフォンのときのコンテンツビジネスの時代で、主役の1社だった会社です。
それをつくっていた一人が水野さんという感じですよね。大学生のときの過ごし方から、クリエイター的な、何かをつくることが好きとか、自発的にやりたいことをやるとか、そういう感じですよね。
水野:起業家という感じじゃなかったですけど、社会で普通にサラリーマンとして生活するみたいなイメージはなくて。10年くらい、唯一の会社員時代を寺島情報企画で働きましたね。
手嶋:水野さんは、そこから、寺島情報企画の中で大出世をするんですよね。そこの自慢話をしてもらってもいいですか?
水野:ガラケー時代の歴史になぞらえて話すので、話がめちゃめちゃ古くなっちゃうんですけど。2000年、2001年、2002年くらいって、着メロとか、着うたとか、そういうものが出はじめて、普及しはじめていた時期です。その当時は、そもそも、モバイルコンテンツは、iモードとか、EZwebとか、月額いくらみたいなサービスで買うしかなかったので。基本的に「モバイルインターネット=通信キャリアがやっているコンテンツサービス」みたいな感じだったんですよね。
僕は、寺島情報企画で、最初は『DTMマガジン』で雑誌の編集者として入社したものの、世の中的に雑誌じゃなくてモバイルコンテンツがきているぞという話があがり、最初に着メロ/着うたのサイトをつくりました。職種で言うとコンテンツプロデューサーですかね。
当時は、既得権益じゃないですけど、サイトをつくること、公式サイトを立ち上げること自体が、けっこう難しかったので。その中で、大手の企業やベンチャーがしのぎを削っていました。
手嶋さんは覚えているかもしれないですけど、iモードの公式サイトという中でランキングがあって、上位にいくと、ユーザーがたくさん入ってくるので。ひたすら、iモード公式の中のメニューのトップにどうやっていくかというのを、コンテンツをつくりながら考えるということをやっていて。ジャンルは、本当に多岐にわたっていました。
自分がやったサイトで挙げると、着メロ、着うたもやりましたし、電子書籍もやりました。それこそ、マックスむらいさんと占いのサイトを一緒にやったり、フジテレビさんと着せ替えとかサイト、109と着せ替えのサイトをやったり。あとは、ヘルスケア、コミック、デコメみたいな感じですね。
2000年、2001年くらいに、iモード上のコンテンツ、モバイルサイトが一通りあったんですけど。今、世の中にあるサイトって、けっこう無料のものも多いですけど。有料のサブスク型で、コンテンツサービスとして配信されていて。それをひたすら立ち上げる仕事というのを、10年のうち7年くらい、ずっとやっていた感じじゃないですかね。
手嶋:一つのサイトが一つの事業とカウントすると、新規事業をめちゃくちゃ立ち上げまくっているということですよね。
水野:新規事業をめちゃめちゃ立ち上げたので。いまだに、いろんなジャンルでいろんなコンテンツを自分の会社で立ち上げてからも、少しずつピボットしながらやっていますけど。コンテンツを立ち上げるということ自体は、正直、何のコンテンツを立ち上げるにも、そんなに億劫じゃないというか。その7、8年でいろんなサービスを立ち上げたので、サービスを立ち上げること自体は、慣れているかなという感じがしていますね。
手嶋:その中で一番の大ヒットはデコメですか?
水野:そうですね。デコメのサイトを、2003年か2004年くらいにつくりました。
手嶋:聞いている人は、デコメが分からないかもしれないですね。携帯のメールに貼れる画像が、なぜか当時はバカ売れしていたんですよね。
水野:絵文字があって、絵文字の延長線上で。今で言うとスタンプですけど。もうちょっと、絵文字以上の表現ができるGIFとかスタンプみたいなものがメールで送れるというのが、2005年くらいに爆発的に流行って
元々、絵文字もドコモだったんですけど。ドコモが絵文字をさらに拡張しようという形でデコメ。HTMLのコンテンツをやろうと言って、企画をつくって、その企画に沿ったコンテンツプレイヤーを集めようと言って、最初、4社か、5社くらい集めてスタートした。たぶん、そんな感じでしたね。
手嶋:声がかかったということは、有力コンテンツプロバイダの1社に、もうなっていたということですよね。
水野:着メロとか、着うたで、そこそこの位置にいた感じだったので。めちゃめちゃ有力じゃないけど、なんか面白いことをやろうとしている会社だというくらい。大手の会社がけっこう多くて。大手の会社は、当然、少しフットワークが重いということもあって。
着メロとか着うたって、今では考えられないですけど、商社が参入していたので。三井物産とか。商社のビジネスとしてやっているくらいの規模だったので。そこにベンチャー系の会社が入ってきて、フットワークでやれるという意味で、新しいフォーマットや企画が出てくるというところで声がかかったという状況もあった気がしますけどね。
手嶋:デコメの最盛期は、月いくらくらいの売上でしたか?
水野:公表していた情報なので言ってもいいと思うんですけど、だいたい100万人くらいの会員がいたので、その当時200円か、200何十円だったので、月で2、3億円くらいですかね。
手嶋:デコメだけですよね?
水野:デコメだけで。
手嶋:それがサブスクで入ってくるんですもんね。
水野:サブスクで。年間で30億円から40億円くらい。
手嶋:ARRだとカウントすると、今の流行りに乗じてすごく適当な話をすると、ARRが30億円のビジネスなので、バリエーション500億円くらいで調達できたということですね。デコメ事業で。
水野:そうだと思いますね。サブスク風に言うと、良く見えますけどね。
手嶋:そんな時代もあり。水野さんは、ある時代、デコメキング、デコメの王だったという話は、ここからの話に繋がってきます。僕が会った頃の水野さんは、寺島情報企画の100%子会社テクノードをつくって、そこの社長だったんですよね。
水野:そうですね。
手嶋:寺島としてもスマホに進出する、と。テクノードを子会社としてつくって、水野さんを社長に抜擢して。寺島時代は、執行役員までいったんですよね?
水野:そうですね。
手嶋:そこから、子会社社長になって。当時、僕が、スマートフォンのアドネットワークをやっていて、媒体側として水野さんに営業にいったんですね。それが最初の出会いですよね。当時、テクノードというのは、iPhoneが出立ての頃にヒットアプリを生み出していて。水野さんがプロデュースしたのは、Touch the Numbersとかですよね?
水野:はい。
手嶋:それをゼロからつくって、世界中でダウンロードさせまくっていたんですよね。そこのテクノード時代の話はありますか?
水野:そうですね。2008年くらいからスマホの事業をやりたいなと思っていて。前の会社、寺島情報企画でやっていなかった事業は、ゲームの領域だったので。ゲームの子会社、スマホの子会社をつくらせてもらおうという話で、スマホゲームの専業会社みたいなものをつくって。けっこう初期に、何十本もひたすらアプリをつくったんですけど、その中でTouch the Numbersというゲームがヒットして。
これは、あとから聞いたので、本当か嘘か分からないですけど、Googleに買収されたAdMobの中の人から聞いた話ですが、世界の広告収益でも5位か6位くらいまでいったというくらい、とにかくひたすら多くの人にダウンロードして使ってもらって。2010年の日本のゲームのジャンルのダウンロード数は、たしか1位だったと思います。
手嶋:そうですよね。
水野:その当時、とにかく、ダウンロードはされるけどビジネスモデルはないみたいな。アプリを有料で買うしかないというところに対して、広告モデルとゲームを掛け合わせたみたいなメディアの先駆けみたいなものが、Touch the Numbersを含めていくつかできたかなと。それが2010年くらいですかね。
手嶋:そうですね。あとは、らくがきライブとかありましたよね。
水野:そうですね。オンラインでリアルタイムに見ず知らずの人と通信できるというようなアプリをつくって。それもけっこうヒットしたので。その当時は、ゲーム、お絵かき系のアプリ。一応、ゲームというジャンルで言っていましたけど、そんなにジャンルを絞らず、ひたすらカジュアルゲームをたくさんつくって、それをメディアとして収益化するみたいなビジネスを2年くらいやっていました。
僕が辞めたあとも含めると、たぶん、累計1,000万ダウンロードくらいいっているんじゃないですかね。アプリのダウンロードビジネスというか、アプリのビジネスとしては、2年間では、その当時は比較的成功したほうかなと思っています。事業もギリギリ2年いかないくらいで早めに黒転していたので。初期はなかなかマネタイズが難しかったので、そういう意味だと良い事業だったかなという気がしますね。
手嶋:当時、僕も会社の中で、メンバーの何人かでヒットアプリもつくれたりして。その頃は、アプリデベロッパーとして水野さんと一緒に付き合っていた感じですよね。
水野:そうですね。
手嶋:そうこうしている間に、水野さんが起業することになり。僕は、そういうアプリの流れで、水野さんに詳しく教えてもらいながら、アプリにめちゃめちゃ詳しくなって、自分たちもヒットアプリを出せるようになって。ひょんなことからメルカリの山田進太郎さんに会って、投資することになって、そこから投資家っぽくなっていくわけですけど。
水野:そうですよね。
手嶋:そこまでは水野さんと一緒に「こんなアプリを考えましたよ!」みたいなことを、2010年頃はワイワイやっていたんですよね。
水野:そうですよね。CocoPPaはその頃ですか?
手嶋:2013年とか。
水野:もうちょっとあとですね。
チャットアプリの起業、その後の撤退の判断基準
手嶋:水野さんはデコメキングになってヒットアプリを出して、2011年にクオンを立ち上げて11年目なんですね。起業する経緯は何だったんですか?
水野:スマホが10年に一度のチャンスだなと思って。iモードがはじまって10年くらい経って。iモードがはじまって10年くらいのうちの7年くらい、ずっとiモード向けコンテンツビジネスをやっていて、iPhoneが出て、Androidが出て、スマホ向けのビジネスが立ち上がったのが2009年、2010年くらいからです。
ここから10年くらいでスマホのアプリが一つ、iモードじゃないですけど、よりグローバルに広がっていくコンテンツのプラットフォームになるなと思って。ゲームだけじゃなくて、もっと根っこの部分をやりたいなと思ったのが、起業したきっかけですかね。
一事業でやる幅って、なかなか狭いなと。子会社をやっていて、ありがたいことに、けっこう自由にやらせてもらったんですけど。ちょっとやりたい幅が広くなってきたなということで起業したのがきっかけかなと思います。
手嶋:最初につくったサービスは何だったんですか?
水野:2011年8月に会社を作って、10月に本当にLINEさんとほぼ同じようなLOUNGEというチャットアプリを出しました。カカオトークを見て、日本で流行りはじめていて、これをやったら絶対にうまくいくなと。
デコメをやっていたので、メールのコミュニケーションがどんどん進化していくというのと、それがもうメールじゃなくてチャットに移っていくというのは、感覚としてはかなり確信があって。カカオトークとか、アメリカだとBelugaとか、Skypeに買収されたGroupMeとかがあったんですけど。
このへんを見ているときに、日本でも必ずくるなと思っていたので。起業するならこれを基点にやりたいなというのは思っていて。それを考えているうちに、LINEが先にでちゃったので焦ったという感じですね。
LINEが2011年6月くらい。僕が起業を考えはじめたくらいに出て。これは今やらないと駄目だなと思って、急いで起業したみたいなところは、正直あった気がします。
手嶋:僕も、本当に最初の頃、水野さんに事業計画を見せてもらったことがあったんですけど。今思うと、すごい少額の資本で立ち上げる計画でしたよね。
水野:そうですね。当時VCもぜんぜんなかったので。やりたいことがあるけど、どうやってお金を集めたらいいか、どうやってやればいいか分からないので。とりあえず、近くにいるメンバーで、なんとかやるだけやってみよっかという感じで、けっこう無理くり立ち上げたみたいな感じではありましたかね。
手嶋:当時のエピソードとして。今は大投資家ですけど、DCMの本多さんがいて。彼はグローバルの投資家なので。本多さんは、僕の大学の極真空手同好会の先輩なんですけど。カカオに投資し、カカオジャパンを立ち上げようとしていて。
日本の責任者を探していたんです。僕は、ひょんなときに「水野さんという友達がチャットアプリで起業していますよ」と言って、本多さんが興味を持って3人で飲みにいったりしましたよね。
水野:ありましたね。その当時、それくらいチャットアプリに精通している人が少なかったので。自分はチャットは絶対にくると思っていましたけど、LINEが出始めの頃でも、周りでは、まだまだメールだよねと言っている人のほうが多かった気がしますけどね。
手嶋:LINEが最初のCMをベッキーでやったとき、僕はとち狂ってんなと思っていましたけど。マネタイズがぜんぜんできないのに、なんでこのCMを打っているのかって。僕も当時は投資家ではなくアプリ事業者だったので。
水野:2011年11月頃だったので。僕もまさか、マネタイズを一切していないアプリがテレビCMを打つなんて、それ以前はたぶんなかったと思うんですよね。ゲームの会社がCMを打ったりするのは、マネタイズ前提でやっていましたけど。
まったくマネタイズしていないアプリがCMをガンガン打つっていうのをはじめて見て、あれはけっこう衝撃だったというか。あのタイミングで、あれのディシジョンができたのは、LINEが勝った大きな要因のうちの一つだと思うので。
手嶋:LINEが出てきたし。LINEが当たりそうだというときに、思い切って投資もできて。かつ、ライブドアの技術陣も、もう統合していたので。LINEが急成長したときに、あのトラフィックを裁けたということですよね。
水野:そうですね。ライブドアのメンバーが入っていたのかどうか分からないですけど。でも、結局、カカオトークがすでに韓国で流行っているというバックボーンがあって。やっぱり、ちゃんとしたプロダクトをつくれば伸びるという感覚はあったんだろうなと。
今にして思うと、そこに先行投資でお金を突っ込むというのは、割とVCがたくさんできて当たり前になりましたけど。その当時は、僕はその発想がまったくなかったので。
手嶋:それをやったのは、グノシーとかメルカリですよね。彼らは2周目の起業で、そういう発想を持っていましたよね。スマートフォンアプリの起業でも。
水野:そうですね。踏み込み方のタイミング、ここだというところが、見ていてすごいなと。このタイミングで踏み込むんだと。僕らからすると早いよなと。事業家っぽい観点で見ると、けっこう早いよなというところで、だいぶ、2段階、3段階、踏み込んだところが、2010年初頭は一気に伸びていったなという印象はありますかね。
手嶋:これは失敗だと、自分の中で確信を持ちはじめる時期ってあるじゃないですか。愕然としたんですか? それとも、そのときは次のネタを持っていたんですか?
水野:2年くらいは頑張ったんですけど、最初の1年間は、絶対にまだまだどうにかなると思っていました。どういうイメージを持っていたかというと、今、当たり前ですけど、LINE以外のチャットって使わないじゃないですか。
でも、その当時は、LINE以外にいろんなチャットを2個、3個くらい、皆が使い分けるんじゃないかというイメージがあったので。この友達とはLINEだけど、この友達とは別のチャットアプリを使うよねというのがあるかなと、1年くらいは思っていましたね。
なので、ちょっとかわいい系に寄せたりとか。エリアを日本じゃなくて、タイとか他の国に絞っていってフォーカスをずらすことで、勝ち筋をつくっていけるんじゃないかなというのは、1年目くらいで。
2年目は、これはちょっと無理だなというふうに思いはじめました。どういうふうにずらしていくかというのと。ずらしていくときに、今やっているチャットアプリ事業のノウハウをうまく下敷きにしてやっていける事業はないかなということで、新しい事業を探していくみたいな感じがあったかなと。今、振り返ると思いますかね。
スタンプ事業への転換/実績を活用した獲得戦略
手嶋:その過程でも細かい事業、auスマートパスとか、スゴ得とか、キャリアと連動した事業。僕も昔やっていたんですけど。そういうのも立ち上げながら。
ただ、大枠は、自社キャラクターを生み出して、スタンプとか、グローバルに広めて、広告プロモーションでやっていくというところが軸足ですよね。チャットアプリからどういうふうに今の事業へ移行していったんですか?
水野:チャットアプリをやりながら、スタンプの事業が、まさにLINEで立ち上がってきて。僕らも、当然、スタンプの事業をやっているうちに。元々、デコメのサイトをやっていたというのもあって、得意なんですね。
プラットフォームレイヤーではなく、コンテンツレイヤーのほうが、中にいるメンバーも僕自身も割と勝ち筋が見えるという部分で。スタンプをやっていく中で、やっぱり、デジタルコンテンツのプレイヤーになっていこうかなと、プラットフォームをやりながら思ったのが一つなんですけど。
そのときに、チャットを軸にしたデジタルコンテンツでいくと、やっぱりスタンプかなということで。スタンプにフォーカスして、事業をやっていこうと。
やっていくときに、スタンプをつくるプレイヤーもいるので、LINEはもちろん国内に競合がたくさんいて。LINEがやっている絵文字とか、デコメとか、スタンプのカルチャーって、日本やアジア独自のものなので、これを他のチャットアプリが真似しはじめるというのが、ぽちぽちと見えはじめて。ただ、真似をしているんですけど、Facebookにしても、WeChatにしても、ぜんぜんうまく真似できていないなというコンテンツというのが見えていたので。
であれば、日本以外のチャットアプリに対して、いわゆるコンテンツを僕らがちゃんとつくってフォローしていくという形ができると、コンテンツのプレイヤーとしては広がっていけるんじゃないかなと思って。
最初は、デジタルコンテンツの会社として、スタンプを世界に広めていくということをやっていて。その延長線上で、デジタルコンテンツとして広げていったものがキャラクターとして認知されて、キャラクタービジネスに転じていったみたいな。流れとしては、そういう感じの順番で流れていく感じになっていますかね。
手嶋:思考回路としてはそんな感じだったとして。とはいえ、スタンプって、はじめた頃はビジネスモデルにはなかったですよね? 有料化されていたんでしたっけ?
水野:日本と韓国は有料だったので。日本向けにやるだけだったら、スタンプ有料でやっていましたかね。
手嶋:そこで、最初からけっこう売上があったんですか?
水野:いや、最初はそうでもなくて。最初は、いわゆる有名なキャラクター、それこそキティちゃんとかディズニーとか、そういうものしかやっていなかったので。ある種、そこに僕らの強いIPを持っていなかったので。最初は、つくるところを手伝ったり、そういう形で入っていましたかね。
手嶋:受託っぽい感じとか?確実に売り上げながらノウハウを積んでいくみたいな。
水野:そうですね。
手嶋:LINEは最初、舛田さんに食い込んだり、LINEの偉い人と繋がったり、そういう世界観ですか?
水野:舛田さんは昔から存じ上げていますけど、スタンプのときは……。最初、めちゃめちゃ、舛田さんにというよりは、普通にスタンプをつくって出してという感じだったと思いますけどね。
手嶋:LINEは日本の人だからアプローチはしやすいですよね。
水野:そうですね。そこは普通にできていました。
手嶋:今、取り組みが深いグローバルプレイヤーは、FacebookとWechatですか?
水野:そうですね。今、Facebookは、グループのWhatsAppの方にも提供していますし。あとはWechat、韓国のカカオトーク、ベトナムのZalo、インドのHikeとか。チャットの大型プレイヤーは、一通り全部、直接繋がってやっていますね。
手嶋:そこは、やれている人って、日本ではほぼいないと思うんですけど。そこはどうやったんですか?
水野:スタンプ・絵文字・デコメ伝道師みたいな、エバンジェリストみたいなポジションで自分を置いて。やっぱり、チャットアプリ側にスタンプをやりたいというニーズがめちゃくちゃあるものの、スタンプをどういうふうにやればいいかというのが、日本以外のプレイヤーは分からなかったんですよね。なので、そういったプラットフォーマーに対して「スタンプとは」みたいな話を直接コミュニケーションして。
手嶋:普通は直接コミュニケーションできないじゃないですか?どうやってそこにたどり着くんですか?
水野:けっこういろいろなパターンがありますよ。人の紹介でいくケースが多かったですけど。中国とか、Wechatとかは、その当時、中国の会社と取引をできる会社はなかなか少なかったので。いろんなルートで。韓国ルート、日本のルートで4、5人くらいを紹介してもらっては、途中でぜんぜん違う人が出てきてみたいな感じで。Wechatに関しては、あるとき、行かなきゃ駄目だなと、謎の使命感がメラメラと働いて。
深センに、Wechatで繋がっている人の繋がっている人みたいな人がいたので、一回会いにいって、その人と丸半日くらい一緒にお茶を飲んでいたらまた知人を紹介すると言われて、翌日その人に会いに行きました。さらにその人からテンセントで働いている人に会えると言われて広州まで行きました。1週間くらいがら空きのスケジュールで中国に行き、友達の友達の友達みたいな感じで繋いでもらったみたいな(笑)。Wechatに関してはそうでしたね。
手嶋:なるほど。まず、日本で実績があって、相当詳しいぞというのを思わせつつ。実際に実績も少しずつ積んで。かつ、それを手繰り寄せるような動きをとにかくしていたと。
水野:そうですね。なので、実績をちゃんと話せれば、一緒にパートナーシップを組めると思っていますけど。そもそも、今以上に、グローバルのプレイヤーと接点をとることが難しかったので。そこは、けっこう気合いで(笑)。
本当に知り合いの知り合いの知り合いで繋がっていったというような感じではありました。その当時、知り合った人が出世していたり、重要なキーマンになったりしているので。いまだに、人の繋がりというのは、グローバル、どのエリアにおいても生きているかなという気がしますけどね。
現在のクオンの事業と、キャラクターの生み出し方
手嶋:今のクオンのビジネスモデルをすごい単純化すると、自社でキャラクターを生み出して、世界中のプラットフォーマーのスタンプに出してもらって、有料のものも無料のものもあるけれど、無料のものもたくさん使われるので影響力が出てきて、それを元に広告プロモーションのビジネスになったり、IPを使ってもらったり、グッズが売れたり、そういうビジネスになっているという理解で良いですか?
水野:そうですね。なので、基本、デジタルコンテンツをマネタイズするというBtoCのビジネスと、広告に使ってもらうという広告のビジネス。いずれも自社のキャラクターをビジネスの主に置いているということがメインですね。
手嶋:今、お金の売上でいくと、海外のほうが大きいんですか?
水野:国内で海外の市場の売上も一部関与しちゃっているので、なんとも言えないですけれど。まだ日本のほうが多いですけど。でも、もう、たぶん、だんだん追い抜くくらいになってきています。
手嶋:スタンプの流通量でいくと、圧倒的に海外ですかね?
水野:そうですね。スタンプの流通量とか、キャラクターの認知度でいくと、圧倒的に海外になっています。
手嶋:このリスナーの人は、そこらへんをぜんぜん知らないと思うんですけど。この国でこのキャラがめっちゃ流行っているよというクオンのキャラでいくと、例えば? ベタックマとか?
水野:絵がないのでちょっと伝わりづらいんですけど。人型のクマでいくと、キモ激しく動くベタックマというキャラは、日本と韓国のスタンプランキングでずっと1位でしたし。あと、うさぎゅーん!という、うさぎが激しく動くキャラクターについては、タイとか台湾とか、いろんな地域のスタンプマーケットで1位ですし。
あとは、Facebookを通じて広がっていくところだと、シュガーカブスというカップルのクマがいるんですけど、そのクマのキャラはメキシコだけで1億ダウンロードか、もっとかな。
手嶋:メキシコで局地的に流行っているんですね。
水野:なので「キャラクター=チャットのプラットフォーム」だったりするんですけど。チャットのプラットフォームの影響力が強いところで、キャラクターも一緒に流行るみたいなこともあるんですけど。僕らは、この地域向けにやるぞというよりは、チャットプラットフォームの流通に乗っけて、そこで人気になったところをビジネスとして深堀りしていくみたいな形を、この数年間はやっている感じですかね。
手嶋:キャラクターでいくと多産多死なんですか? それとも、だいたい一定の割合で当たっているんですか?
水野:もう、300、何百キャラつくって、そのうちビジネスになっているのは10とか、そのくらい。
手嶋:途中でやめているもののほうが多いんですか?
水野:そうですね。そういう意味でいくと、スタンプって、SNSの運用みたいな感じとはちょっと違って、勝手にユーザーさん同士が送り合ってくれている間は、キャラがアクティブなので。
僕ら側が、そのキャラクターをこういうキャラだよとずっとコンテンツをつくり続けなくても、使ってもらっている間は、使っている人たちの中でそのキャラクターは生きているという意味では、そんなにめちゃめちゃひたすらコンテンツをつくり続けるという形にしなくていい。それは、一つ、特徴的かもしれませんね。
手嶋:特に初期につくったキャラが当たったという感じですか?
水野:そうですね。WeChatとか、Facebookとか。初期に参入したときに当たったキャラが、いまだに認知があるというのがあると思いますね。
手嶋:それはどうやって生み出したんですか? 水野さんと社内のデザイナーの人で膝詰めで「いや、こういうのがいいよ」って、そうやってつくったんですか?
水野:最初は本当に分からないので、1周目でいくと、本当にとりあえずたくさんつくりたいものをつくるという感じでつくって。1周目をつくって、いろんなチャットプラットフォームで出すじゃないですか。出すと、明らかに傾向が出るんですよね。
クリエイティブの世界やキャラクターの世界で、データドリブン的なことを言う人はあまりいないんですけど、僕らは割とデータを見ていて。どの国でどの動物がどういったメッセージを使って使われているかということ。プラットフォーマーにもよるんですけど、様々なデータをもらえるので。
それを見ていったときに、今まではどっちかというと、ユーザーさん、お客さんの声を聞いて「このコンテンツはここが良かったんだね」というフィードバックがあったものが、あるキャラクターやクリエイティブの領域がデジタルデータで「ここが良いんだよ」と、プラットフォーマーに教えてもらうみたいな経験をして。それを元につくってみようかという形。
厳密に言うと、1周目より、2周目くらいにつくったキャラが割と当たっているかもしれないですね。出していく場所によっては、色、形、動物、メッセージ性。メッセージ性も、アジアとアメリカではぜんぜん違うので、そのへんがだいぶポイントになっているかなとは思います。
水野氏のクリエイターマネジメントと組織運営の考え方
手嶋:そんな感じでチャットアプリからグローバルIP事業へ。ゼロからIPを生み出して。ある種、今時のやり口でIPを育てていくという事業が成功しつつあるという感じだと思いますけど。水野さんは、その過程で、グローバル拠点は今3拠点ですか?
水野:そうですね。中国とタイとベトナムですかね。
手嶋:そこを組織運営できていること。あと、デザイナーのマネジメントが、昔から上手ですよね。そういう意味でいくとクリエイターのマネジメントと言うんですか?
水野:そうですね。どっちかというと、クリエイターネットワークをつくってというよりかは。僕は、社内にスタジオをつくって、社内スタジオのクリエイターマネジメントみたいなほうですけど。それは、比較的得意かもしれないですね。
手嶋:グローバルになると、拠点をやっている若者って、優秀な方を採用して、抜擢して、それぞれ、やる気を持ってやってもらえている状況だと思うんですけど。水野さんの組織運営術って? 正直、水野さんは経営者でいくと脱力系じゃないですか(笑)。そんなすごそうなこととか、かっこよさそうなこととか、対外的にすごく言っていく感じでもないから。
水野:確かにそうですね。
手嶋:そういう優秀な若者を集めて、責任あるポジションにつけて、長期間働いてもらうとか、デザイナーとかクリエイターをインハウスでマネジメントし続けるとか。いわゆる、今のスタートアップでやりたいっすみたいな若者とは、またちょっと違う人たちを集めてうまくいっていると思うので。
水野:そうですね。
手嶋:そこらへんは、どういう考え方でやっているんですか?
水野:でも、グローバルの拠点に関しては、そもそも、僕らは、割と初期からグローバルをやるぞと公言しているので。グローバルに興味がある学生とかは、割とインターンとかで集まりやすいという環境が元々あって。
インターンとかでやっていく中で、本当にこの若者はやる気があってグローバルにいけそうだなという場合は、ある程度、予算と権限を渡して、そのままグローバルにいってもらうみたいなことはやっています。
失敗した人もいますし、失敗したこともたくさんあるんですけど。そこを許容しながら広げていったというのと。結局、例えば、キャラクターのアジア展開とか、キャラクターの広告業、マーケティング業、インターネットでのマーケティング業とかって、やったことがある人はいないので。
やったことがあるジャンルだと、経験がある人とか、年齢がいっている人とかのほうがうまくいくんですけど。そうでもないジャンルって、むしろ、あまり固定概念・固定観念がないほうがうまくいくかなと。
要所要所だけ、ヒアリングをしながらアドバイスをしていけば、そこで逆にワークするかなというのが、根本的な考え方としてあって。それを何人かやっているうちに、そのポイントをしっかりと掴んだ責任者がグローバルで育ってきているというような感じですかね。グローバルの展開については。
前半はここまでです。後半はクオンとwwwaapの合併、「株式会社Minto」の設立の秘話をぶっちゃけていただいていますので是非ご覧ください。
-
 Podcast(書き起こし記事)
Podcast(書き起こし記事)#27 創業3年で十数億円調達。KiteRaが描く「社労士×事業会社」の経済圏構想 ー KiteRa植松隆史...
-
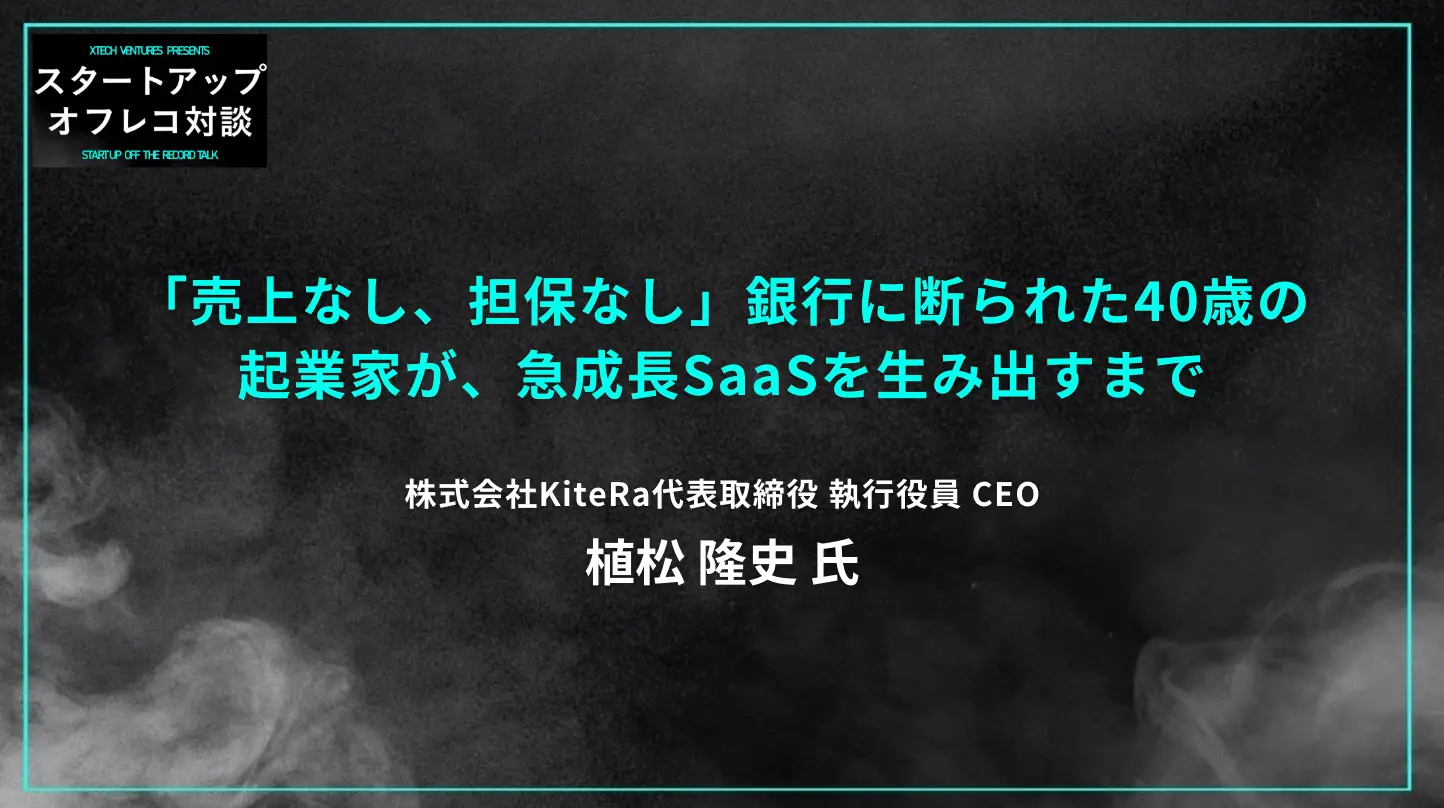 Podcast(書き起こし記事)
Podcast(書き起こし記事)#26 「売上なし、担保なし」銀行に断られた40歳の起業家が、急成長SaaSを生み出すまで ー KiteRa...
-
 メンバーインタビュー
メンバーインタビューITコンサルから、未経験でVCの世界へ。技術バックグラウンドを持つキャピタリストがXTech Venture...
-
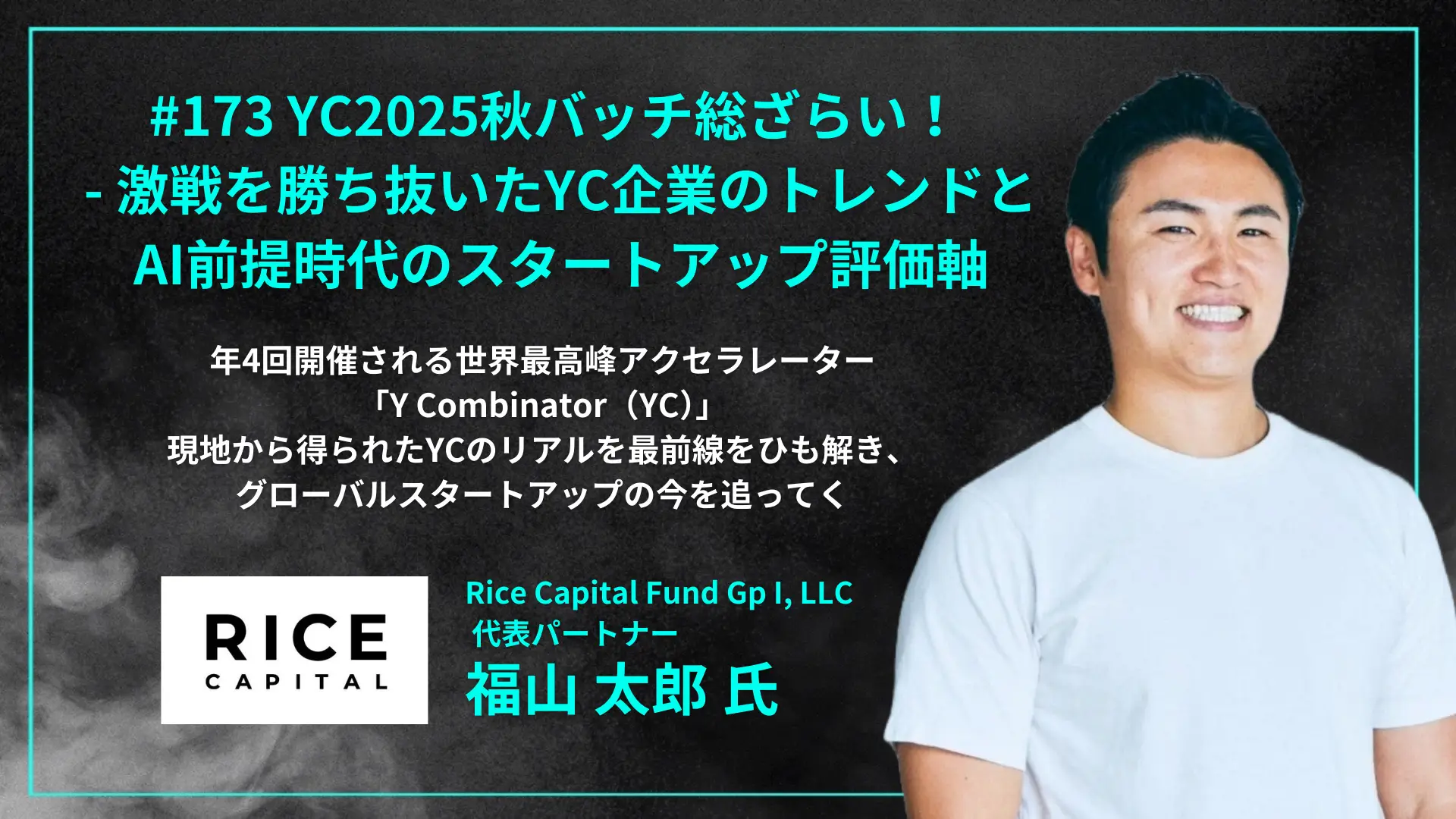 Podcast
Podcast#173 YC2025秋バッチ総ざらい! - 激戦を勝ち抜いたYC企業のトレンドとAI前提時代のスタートアッ...
-
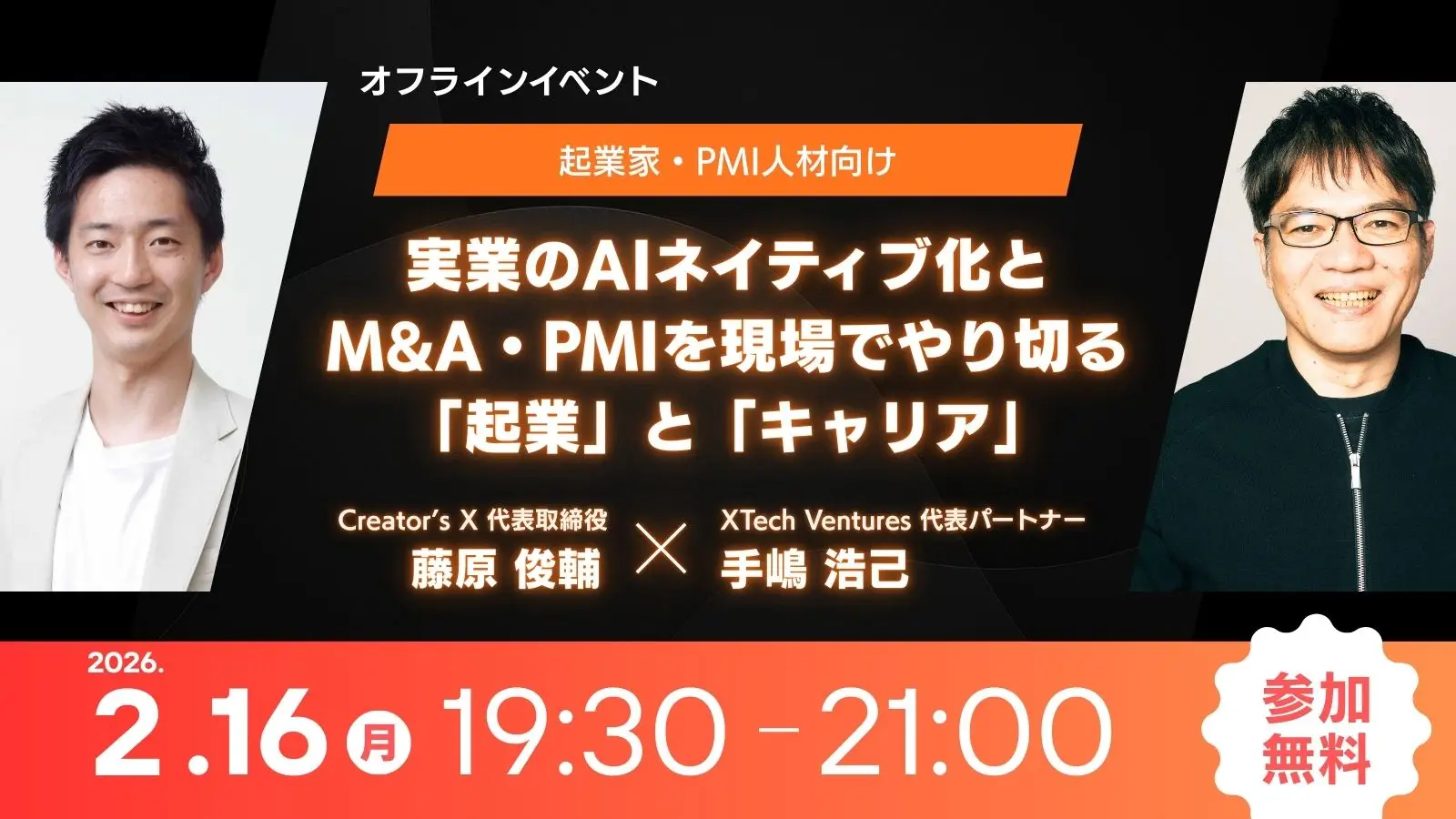 イベント
イベント【イベント告知】実業のAIネイティブ化×M&A・PMIを現場でやり切る「起業」と「キャリア」を語るトークセッ...
