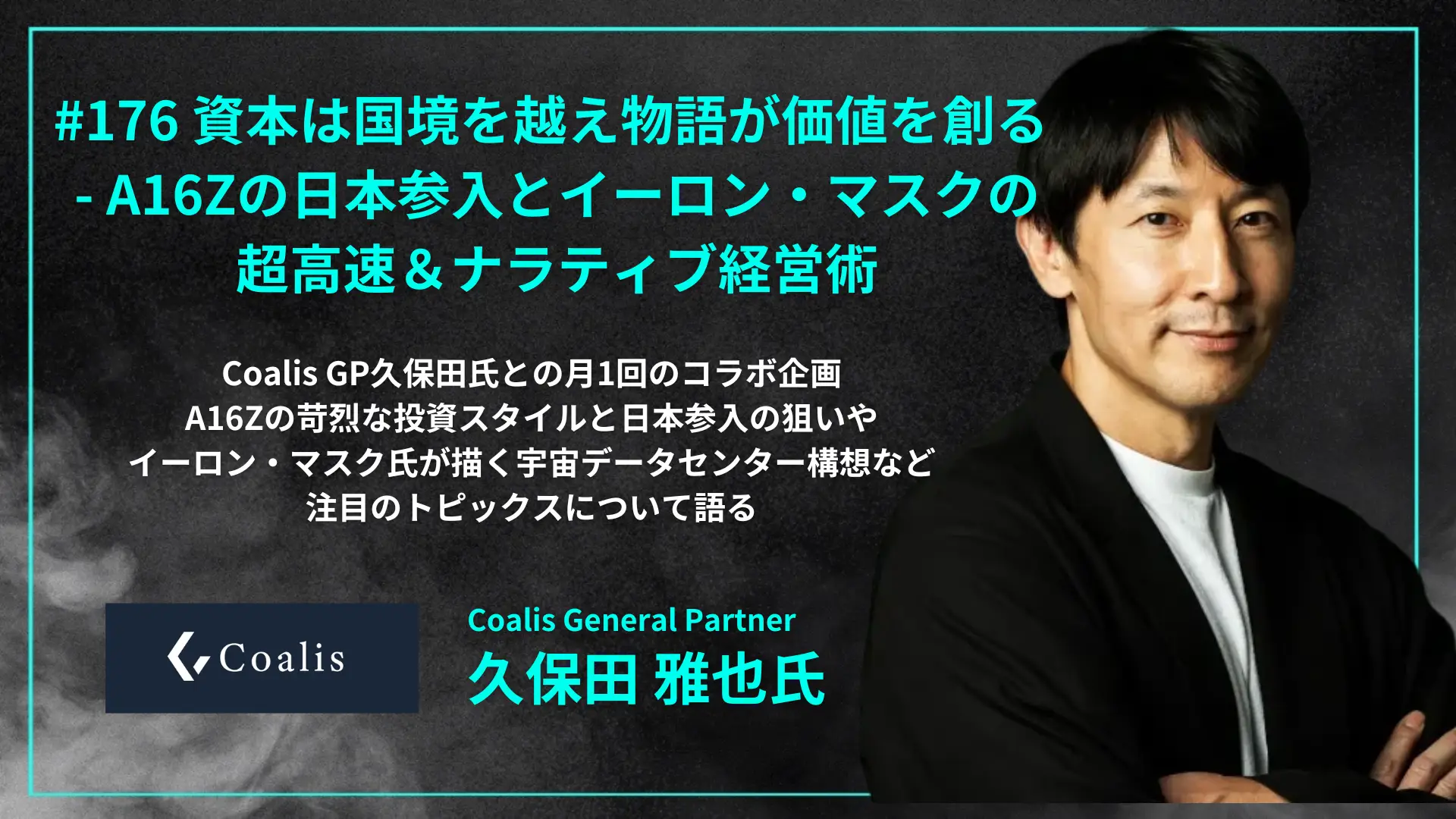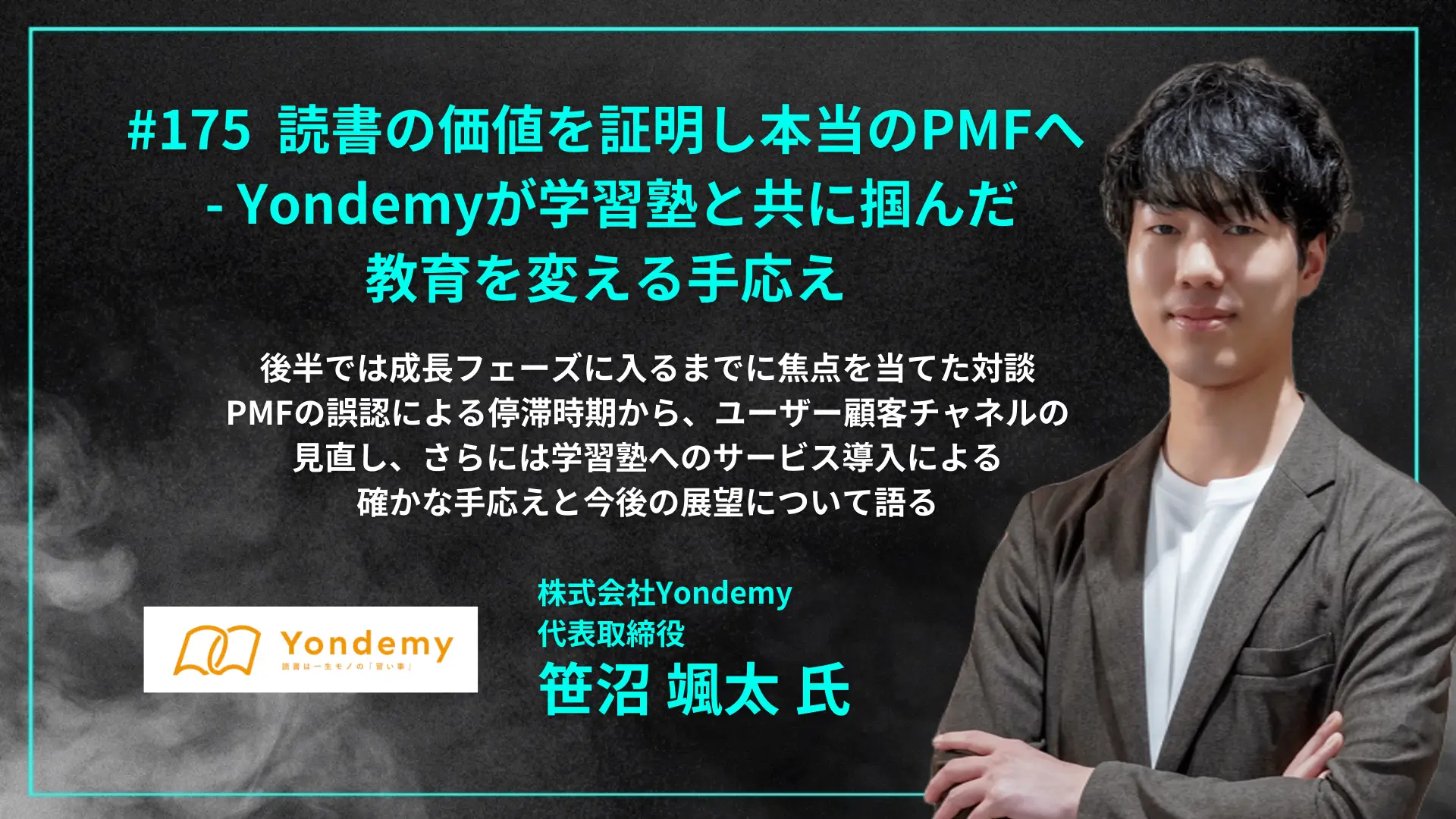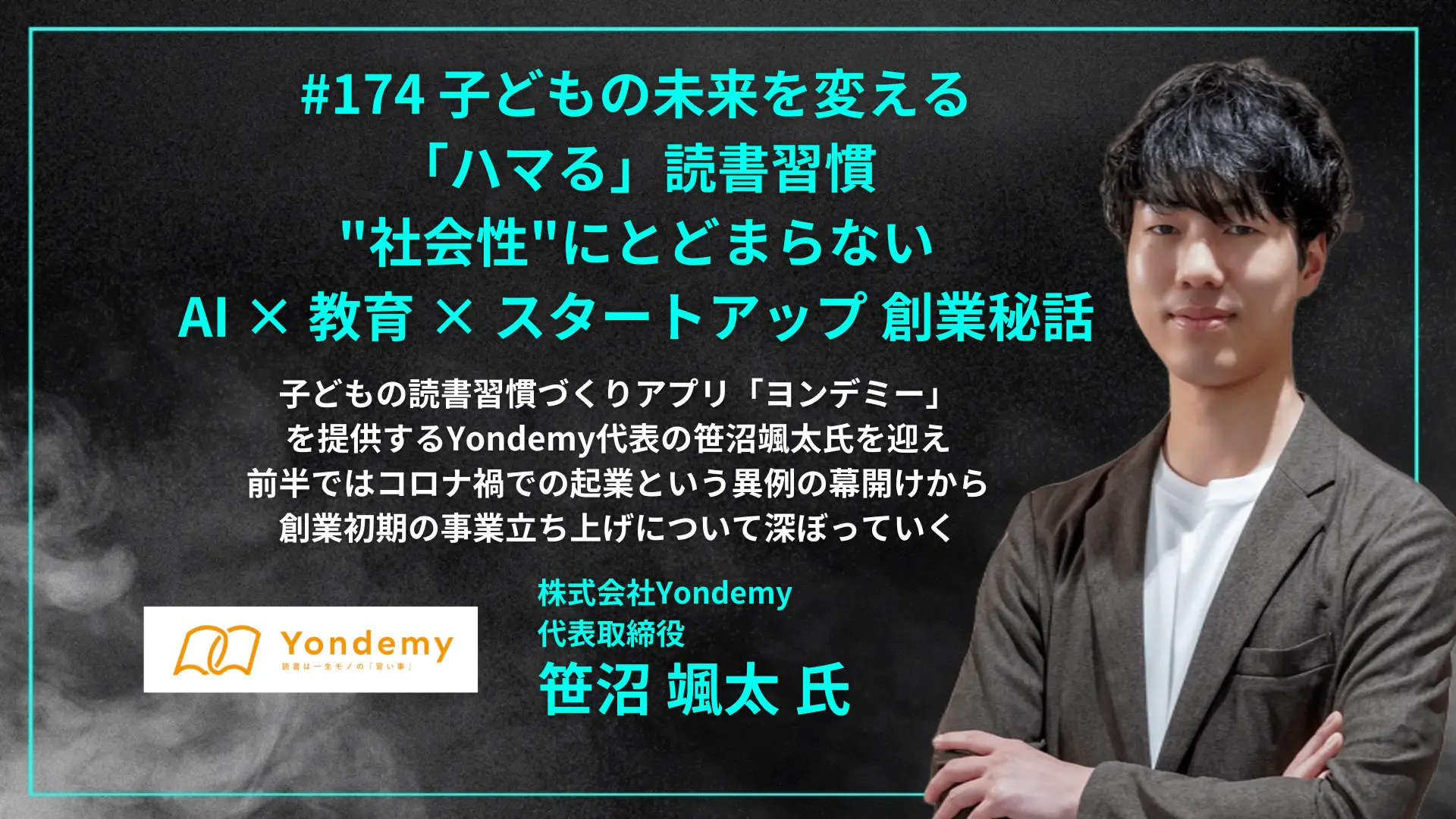#9 セーフィー、フォトシンスの成長可能性とは? IoTスタートアップ起業家が語る上場企業2社の考察ー Strobo 業天亮人氏
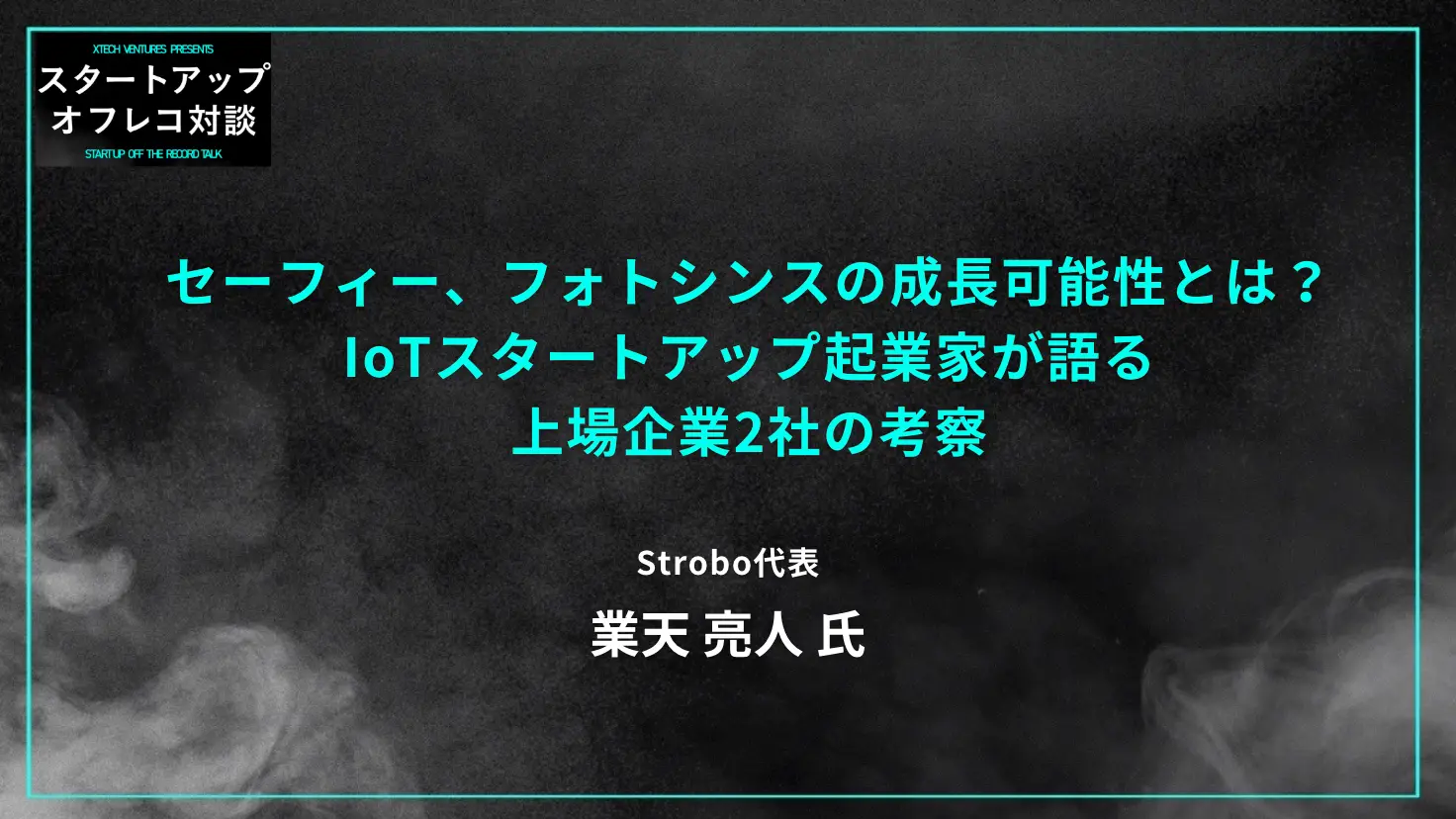
「スタートアップ オフレコ対談」は、XTech Venturesの代表手嶋とゲストの方をお呼びして対談する番組です。今回は2015年に設立し、ホームセキュリティ×IoT領域で事業を展開するStrobo社。同社のCEOである業天亮人氏をゲストにお迎えします。
前編では、上場した2社のIoTスタートアップ「セーフィー」「フォトシンス」について、成長可能性資料を見ながら考察します。(ネットで閲覧可能ですので、ぜひ資料を参照ください)
スピーカー
・業天 亮人氏(@gyoten)
Strobo代表
・手嶋 浩己(@tessy11)
XTech Ventures代表パートナー
目次
#IoT領域としてのセーフィーの立ち位置
# セーフィーのビジネスモデルについて
# 多種多様な業種で活用されるセーフィー、今後の成長見通し
#6人で共同創業したフォトシンス、主力事業のAkerunについて
#地方展開、住宅市場参入——フォトシンスのマーケットポテンシャル
※記事の内容は2021年11月時点のものです。
#IoT領域としてのセーフィーの立ち位置
手嶋:今回はIoTのスタートアップについて語り合いたいと思います。セーフィー、フォトシンスとIoTスタートアップの上場が続いているので、これは元祖IoT起業家を呼んで語り合おうじゃないかということで、今回はStrobo社の業天さんに来ていただきました。
2015年にIoTスタートアップを起業して、今まさに業界の最前線にいる業天さんと、セーフィーとフォトシンスのすごさを語り、後半は業天さんが代表を務めるStrobo社の構想を聞いていく流れです。業天さんと私はゆるい友人ぐらいの距離感で、ここ数年お付き合いがあるんですけど。簡単に自己紹介していただいてよろしいですか?
業天:初めまして、株式会社Strobo代表の業天と申します。Stroboは個人向けのIoT家電のスタートアップで、アプリセンサーを使った格安セキュリティサービスの「リーフィー」を提供しています。低価格のセコムやアルソックのようなサービスと言うとわかりやすいでしょうか。これまでは比較的裕福な家庭しか使えなかったホームセキュリティを、IoTの力で低価格にして、より多くの人に使ってもらおうと事業を展開しています。よろしくお願いします。
手嶋:業天さんが創業したのが2015年。LayerXの福島さんとかが大学の同級生でしたっけ?
業天:福島くんは、同じ大学ですが、一つ上の先輩です。東大起業サークルTNKの仲間ですね。
手嶋:そこで一緒だったんですね。創業の2015年はスマートフォンアプリサービスの起業が盛んな時期だったと思うんですけど、どうしてその時期にわざわざIoTのスタートアップを起業したんですか?
業天:もともと僕は2011年の大学3年生のときにIoTのベンチャーを起業してまして。スマートリモコンを提供するPlutoという会社だったんですけど、その時は全然IoTという言葉が流行っていなかったので「インターネット家電のベンチャー」と呼んでいました。
自分自身は、未来のソニーになれるような家電ベンチャーを日本から作りたいというこだわりがあって、アプリにわき見もふらずに2社とも家電ベンチャーをやっていたんですよね。
手嶋:なるほど、ソニーが原点だったわけですね。ここからはセーフィーとフォトシンス、2社の成長可能性資料を見ながら話していきます。ネットで見られるので、皆さんもぜひ見ながら読んでいただけるといいかと思います。セーフィーの資料4ページ目、設立年月が2014年ということはStroboとほぼ同期ですね。
業天:フォトシンスもそうですけど、この時期に起業したIoTのベンチャーが多いんですよね。
手嶋:この時期に何かあったんですか?
業天:セーフィーはそこまで関係ないかもしれないですが、Bluetooth Low Energyという無線通信の仕様がiPhone4Sに対応して使えるようになったのがちょうど2013〜2014年。この時期に起業したIoTベンチャーが非常に多いのは、この出来事が背景にあります。
手嶋:なるほど。この時期にSo-netグループもモーションポートレートという、顔写真をアニメーション化できる面白いアプリを出していますね。使っているテクノロジーはメインの事業と共通していて、全く違う事業へとスピンアウトしたということですね。主要投資家には、事業パートナーがたくさん入っている。ここはあとでも触れますね。
7ページ目に行くと、課金カメラ台数が現在13万台弱とあり、どう伸びてきたかというグラフがあります。業天さんは、これをみて思うことはありますか?グラフの推移について。
業天:シンプルに、綺麗に伸びているなと。ただセーフィーが上場したときに、僕も含めて皆が驚いたのは、直近2020年の3Qから4Qにかけての急成長ですね。今までの時間軸で見ると目立ちづらいんですけど、ここを切り取って注目すると一気にまた伸びているので、何があったんだろうと気になりますよね。
手嶋:すごく雑に言うと、コロナの影響というか、非接触が前提になってきたとか、そういう文脈なんですかね。
業天:かもしれないですし、パートナーセールスがやっぱり多いので、どこかのパートナーでのセールスがどかっと来たとかかもしれません。
手嶋:8ページ目で、昨年度の売り上げが50億で、ARRだと45億。NRRのレート、彼らでいうと直販とパートナーセールスがあるんですけど、直販ルートは順調にアップセルできていて138%ですね。なので、新規顧客を取らなくても既存顧客だけで成長していくモデルになっていると。
彼らはクラウドモニタリング録画サービスという概念でシェアが47.5%だと自分たちで言っているんですけど、A社B社がどこか業天さんわかりますか?要するに業界2位、3位の会社ということになりますが。
業天:ここはよくわからないんですよね。
手嶋:そもそも、たくさん事業者がいる領域なんですか?
業天:事業者はたくさんいますね。もともとハードディスクや専用モニターやカメラを製造していたメーカーがクラウド対応して参入しているパターンも何社かあるので。ただシェア47.5%と出ている通り、目立ったプレーヤーはやっぱりセーフィーですね。
手嶋:2位、3位の顔が見えない感じなんですね。2位でも15.2%、3位で10.7%と、それなりにシェアはあるんだけど、でもおそらくスタートアップではなく既存のカメラメーカーなんでしょうね、きっと。
業天:そうですね。スタートアップ系ではあまり思い浮かばないですよね。セーフィーと似たところは。
# セーフィーのビジネスモデルについて
手嶋:9ページはビジネスモデルに触れています。彼らは自分たちのことを、クラウド映像プラットフォームを運営している会社だと。ハードウェアのスポット収益とクラウド上のソフトウェアサービスを提供して、リカーリング収益を得ているみたいなんですけど。この事業ドメインの定義については、業天さんはどう見ていますか。
業天:セーフィーはIoTだと分類されがちですが、もはやプラットフォームだなと。それがフォトシンスや弊社と違うポイントだなって思うので。セーフィーはカメラを自社で作っておらず、カメラのOSを作り、かつ、その上で動くサービスを作って各社に販売しています。デバイス開発が発生しないビジネスモデルなんです。
物を苦労して作っているStroboの立場からすると、事業的な効率の面に限れば本当に大きく異なるなと。そこにプラットフォーム感をすごく感じますね。
手嶋:自分たちでやるところとやらない部分の切り分け方がすごく美しい感じなんですかね。
業天:そうですね。
手嶋:ちなみに、IoTのスタートアップでカメラを自分たちで作ってないって不安になったりしないんですかね?そこはもうコモディティな領域だから、どんどん導入メーカーを入れ替えていけばいいやぐらいの感覚なのでしょうか。
業天:セーフィーは、本質的に自分たちがIoTの会社だとは思っていないんじゃないですかね。あまり接点がないのでわからないんですが、本当にクラウドの映像のプラットフォーマーであるだけで、IoTと呼ばれることもあるぐらいの気持ちなのかもしれないですね。
手嶋:先程、急にぐっとこの1年売り上げが増えていて、パートナー経由の販売が一気に伸びたんじゃないかという話がありましたけど。現時点では直販が40%で、パートナー企業がNTT東日本、セコム、キヤノンとそうそうたる企業ですよね。
業天:ここはすごいですよね。
手嶋:それぞれの会社でブランドを作ってやっているのかもしれないですが、これが60%ぐらい商流としてはあると。だからOEMで提供するパートナーもいれば、Safieブランドのまま販売しているパートナーもいるという感じですね。
僕が注目したいのは顧客です。基本法人のイメージだったんですけど、どれぐらいのパーセンテージかわからないものの個人にも販売しているのが図になっています。結構、個人も監視カメラのような用途で使っているんですかね。
業天:いやあ、ウォッチャーとして言わせてもらうと、セーフィーが提供してきたサブスクプランが2つあって、「Safie HOME」のすぐ後に「Safie PRO」が出たという順番。HOMEはたしか2019年にクローズしているんですよね。もうPROに絞りますと。そういう背景があるので、あまり個人顧客はいないんじゃないかなと思います。
手嶋:そうですよね。資料の図では個人と法人が同じ大きさで書かれているじゃないですか。そうするとマーケットがより広いのかなと一瞬思ったんですが、今後狙っていきたい意図があるかもしれませんが、現時点では法人顧客のシェアがかなり大きいはずですよね。
業天:ほとんど法人だと思います。
手嶋:自社が提供するサービスに対して、SaaSをもじった造語をさまざまな会社が作るんですけど。セーフィーの場合は「VDaaS」、Video & Data as a Serviceだと。なんと読むんでしょうね?
業天:ブイダースじゃないですか。
手嶋:ブイダースとしてIoTエコシステムを形成し、デジタルとリアルのプラットフォームとしてさまざまな現場にソリューションを提供すると謳っています。市場規模でいくと、国内だけでも3000万台弱の市場があるのではないかと。彼らはシェアを50%持っているので、そのシェアを維持するだけでも1500万台ぐらい取れるってことですよね。
これが本当だとすると。業天さん、これは感覚的にはどうでしょうか?今彼らの設置台数が13万台弱に対して、市場規模がこの数字だとすると、どういうところにカメラが付いてくのかみたいなイメージとかってありますか?
業天:ネットワークカメラと呼ばれるものは、ペット見守りカメラなども入ってると思うので、そういう意味では3000万台ぐらいあっても全然おかしくないですね。たとえば、コンビニって1店舗あたり何台ぐらいカメラが付いていると思いますか?
手嶋:それはいわゆる無人コンビニとかじゃなくて通常のコンビニってことですよね。3台とかですか。
業天:だいたい8〜10台ついてるんですよ。
手嶋:そんなについてるんですね。
業天:カメラって、特に店舗などでは、死角が発生しないように狭い空間でも大量に使われるんです。事業者は何百万とあるので、盛りすぎだという感覚はないですね。
手嶋:なるほど。わかりました。セーフィーはIPOしましたけど、まだまだ伸びしろはあるぞと、一定の信憑性はあるのかなという感じですかね。続いて、17ページには彼らの製品のシリーズが載っています。このラインナップを見て、業天さんの感想はどうですか、現時点では。
業天:2つあります。やっぱりGOとかPocketシリーズのような、携帯回線を内蔵した持ち歩けるタイプのカメラが出てきたんですよね。工事現場の作業員が作業記録を取る際や、リアルタイムで指示を受ける際に使われているらしいんですけど。仕事上のコミュニケーションや業務改善に使われ始めてるのが、またサービスの幅が広がりそうだなという感じですね。
手嶋:こういった製品展開やパートナーセールスの状況を見ていると、BizDevが得意そうな感じが漂いますよね。
21ページでは、カメラの導入効果が載っています。ある飲食チェーンがSafieを導入して年間のコストが約4600万円から約1700万に減りました。各店舗に出張せずに遠隔でモニタリングができるようになったため、業務報告費や出張費が減ったと記載されています。ああ、そういうところを減らすイメージで提案してるのかと感じましたが、この点はどう思いますか?
業天:もう、なるほどという感じですね本当に。セーフィー自身、「クラウド防犯カメラ」とワーディングしていたりもするんですけど。防犯対策そのものは売り上げを伸ばす施策ではありませんが、コスト削減を謳いつつ、売り上げを伸ばせる側面もあると思うんですよね。モニタリングできる回数が増えるから、的確な指示ができて売り上げが改善しますよとか。防犯からズラして売上に紐づくところに提案できているのがすごいですよね。
手嶋:事業に直接的に役に立つってことですね、「PLに効くカメラ」というような感じの提案なんですねきっと。
業天:防犯の問題点を解決したらアップセルはできないけど、売り上げは無限にアップセルできるじゃないですか。
手嶋:防犯は安心感の提供と、いざとなったときの体制作りってことですよね。そういった観点で建設現場でも使われていますよという感じですね。
# 多種多様な業種で活用されるセーフィー、今後の成長見通し
手嶋:25ページがパートナーセールスについてで、最初の事業はセコム的な事業だったってことだと思うんですけど、そのセコムにも提供していると。セコムの画像クラウドサービスって結構売れているんですかね?
業天:これはどうなんですかね。そこまでまだ見かけませんが、自分がターゲットユーザーじゃないからかもしれません。ちょっとわからないんですけど。
手嶋:先にスタートしているキヤノンやNTT東日本のほうがやっぱり大きいんでしょうね、きっと。
業天:本当にギガらくカメラはすごく見ます。オンライン上でも。
手嶋:それは、宣伝してるからってことですか?
業天:宣伝ですね。セーフィーの売り上げの30%がNTT東日本さんと資料に記載がありましたけど。やっぱりそのインパクトも大きいですし、世の中でギガらくカメラをよく見かけるので、やっぱり気合を入れてるなあとすごく感じます。
手嶋:最近だとAI insideのプロダクトをNTT西日本が1回買い切って。ただ売れ行きがよくなくて翌年契約更新をせずにドカンとAI insideの売り上げが下がって…ということがありましたけど。でもポテンシャルとして、やっぱりNTTグループの販売力はすげえなという感じですかね。
業天:NTTグループのスモールビジネスへの販売力はすごいですよね。
手嶋:基本デフォルトで使わざるを得ないですよね、NTTだと。
業天:商流には必ず入れますからね。
手嶋:NTTは2018年10月、誰もセーフィーに注目していない頃に契約を決めて、売っているという。その数年間の蓄積がでかいのかもしれませんね。
26ページには導入企業一覧があります。幅広く導入されていて、現場系、いわゆる小売・飲食、その他のカラオケとかの店舗系や物流施設、交通施設、工場などはわかるんですけど、オフィスも一定あるんですね。いわゆる監視カメラ的な用途なんですかね?
業天:ではないかと思います。たとえば、エントランスにカメラを設置したいと考える総務担当の方も多いと見受けられますね。
手嶋:リモートワークで社員の出社頻度が下がると、常に人がいる状況ではないから、むしろセキュリティ的には不安ですよね。知らない人が入ってきても気づきにくいですから。それゆえに需要が高まってるのかもしれませんね。27ページは製品の技術面に触れています。基本的にはすごい技術者が集結していますとアピールしていますが、技術的にはどのあたりが難しい領域なのでしょうか?
業天:やはり、ソフトウェアカードなのでクラウドを使ってできないことがないというか。そこで差別化が結構難しいところだと思います。
セーフィーさんの場合は、画像の転送コストがかかると思います。画像をクラウドにアップロードして、ユーザーがそこで確認をすると。セーフィーの通信原価の比率が、サービス部分だけ見ても純粋なソフトウェアサービスにしてはすごく高いんです。そこを最適化するのは結構難しいですよね。あとは自社でリアルタイムに映像のストリーミングを行っている点も、難易度は低くないのかなと思います。
手嶋:でも人数でいくと、2021年の6月末段階でエンジニアが43人なので、わりと少数精鋭。事業の規模からすると、むしろ少ないのかなって感じるぐらいの人数ですね。
業天:人数は少ないですよね。
手嶋:それでARR45億円を作っているんだと意外な感じがしました。続いて、31ページの業績イメージです。業天さんがさっき言った通り、このモデルでいくとクラウド録画プラットフォームではあるので、彼らのクラウド上でどんどん動画データが溜まっていくわけですよね。サーバーコストが非常にかかっているんでしょうか。
SaaSのビジネスなら粗利率がとても高い印象があると思うんですけど、彼らの場合は、リカーリング部分の粗利率でいくと今40〜50%なんですね。それを60%程度まで上げていきたいという構想だと思うんですけど。逆に言うと50%ほど原価がかかっているようですが、これはほぼサーバー代だと思っていいんですよね?
業天:私も、ここは資料を読みながら読み解けなかった部分なんですけど。リカーリング売り上げのところに、カメラのレンタル料金が入っているんですよね。なので、カメラの減価償却が原価に入ってくると。
手嶋:カメラは、彼らから買うこともできるし、レンタルでもできるってことなんですね。
業天:はい、レンタルもあるんですよ。
手嶋:レンタルの比率って結構高いんでしたっけ?書いてないですね。でもそこまで大きな影響がある感じの書き方ではないですけどね、こう見ると。
業天:原価率が下がるにしても、5%とか10%かもしれないですね。
手嶋:逆にやはりスポット収益というか、彼らは基本的にカメラに関してはハードウェアから仕入れて販売しているだけなので粗利率が低くて、15%ぐらいになりますって感じですね。
業天:20%ぐらいハードウェアを仕入れているところでも、きちんと確保できているのが強いですよね。
手嶋:逆に、ここで利益を取る必要があるのかとは少し思います。安くすればさらに売れるのかみたいな。
業天:うーん。パートナーセールスもある関係で、結構そこはいろいろ難しい面があるかもしれないですね。
手嶋:自分たちの製品だけ安くすると、パートナーが販売している製品が売れにくくなるとかはあるかもしれないですね。
業天:はい。あと気になるのは、このスポットの粗利率が2011年で急に下がる点ですね。
手嶋:バルクで導入して、1台あたりの利益率は下がってる可能性はあるかもしれないですね。大口のお客様が増えている影響とか。
業天:この急拡大フェーズにおいて、そういうことをしていたのかもしれないですね。
手嶋:あと、「エッジでの画像処理開始により、収益性向上」とあるんですが、これはどうして収益性が向上するんですか?
業天:たとえば、セーフィーの製品で顔認識をする際に、これまでは画像の映像データをクラウドに上げて、クラウド上で演算して認識していると思うんですけど、それって計算コストがかかるんです。それをカメラのデバイスに搭載しているCPUで行うから、その計算時間分は、安くなるというか原価がかからなくなるというのはあると思います。
手嶋:よくわかりました。ありがとうございます。で、今のARRが45億で、2021年の年末のARR予測が56億。課金カメラ台数も2021年内に15万台まで行くだろうと予測を現時点でしていますね。
33ページでは、リカーリング収益がきちんと積み上がっていることを示す例のミルフィーユ図があって。今後の成長イメージでいくと、35ページの図で見ると、利用用途をめちゃくちゃ広げていくって感じなんですかね?
業天:そうですね。やっぱりそもそもカメラって資料に書いてあった飲食店、商業施設、駐車場とかには既にあるじゃないですか。それをクラウドカメラににリプレイスしていこうというところで。
手嶋:この商品の事業って、事業企画の人は企画が立てやすそうですよね。
業天:そうですね。セーフィー自体の機能がシンプルなので。やっぱりtoB SaaSって結構、特定のメニューを作り込むじゃないですか。飲食業界のクレーム改善とか。だから横展開が不能になってしまいがちです。
自分も使ったことがあるんですが、Safieは機能が本当にシンプルなんですよ。営業企画・事業企画の方のアイデア次第で無限に業界を横展開できるところが、セーフィーのすごいところですね。
# 6人で共同創業したフォトシンス、主力事業のAkerunについて
手嶋:続いてフォトシンスの話題に移ります。同社はより直近に上場した銘柄で、ここも2014年の創業。さっき業天さんが言った通り、IoT起業ブームの世代ですね。ちなみに社長の河瀬さんとの交流はあるんですか。
業天:ありますね。最近はほとんどないんですけど、フォトシンスの設立直前ぐらいに、自分が先にハードウェアベンチャーを一度立ち上げてすでに退任していたんですが、「ハードウェアベンチャーってどうやって作ったらいいんですか?」と聞いてきてくれて、創業メンバー6人のうちの3人とご飯を食べていました。
手嶋:じゃあ、当時はレクチャーする側だったってことですね。
業天:いや、ランチを食べたぐらいですね。僕がそのときに伝えたアドバイスがあったんですけど、「6人で起業って多くないですか?」みたいな。手嶋さんはどう思いますか?
手嶋:6人は多いですね。
業天:多いですよね。けど、結果的にやっぱりその6人が必要だったな、6人が非常によかったなと思っていまして。ハードウェアベンチャーってプロマネしなければならないことが多いので、2〜3人で起業すると人が足りないんですよね。そこでスピード落ちちゃうんですけど、そういう意味で6人でわちゃわちゃやっていくというのは、結果的にめちゃくちゃキーファクターの一つだったんじゃないかなと今なら思います。
手嶋:フォトシンスが何をやっている会社かというと、さっき業天さんがおっしゃっていた「Akerun」という、スマートロックのサービスを提供しています。5ページにあるようなサービス内容で、「Akerun」の入退室管理システム、ハードウェアと同じ名前でソフトウェアも売っているという感じですね。
6ページにKPIのハイライトが載っていまして。ARRだと14億円弱で、サブスク比率が90%、粗利率が82%。セーフィーは粗利率が50%程度だったので、フォトシンスの粗利率は普通のSaaSのスタートアップとほぼ変わらないぐらいでリカーリング収益の部分では出しているのかと思います。
CAGRは、ここ数年でいくと平均130%ぐらい伸びていて、チャーンレートは1.5%。契約者数は3700社。ご存知の方もいると思いますけど、上場後の株価自体は軟調です。売り上げ規模にしては成長率が低いといった評価になっている感じですが、この指標を見て業天さんが思ったことはありますか?
業天:各KPIを見ていると、IoT×SaaSのリアリティが感じられる数字ですね。
手嶋:ちなみに、それぞれの数字はだいたい予想通りでしたか?
業天:そこまでウォッチしてるわけではありませんが、そうですね。セーフィーの数字にすごく驚きがある中で、弊社はフォトシンスさんのほうが近いんですけど。そういう意味ではむしろ求めているイメージ通りの数字な気がしますよね。
手嶋:今まで積み上げてきた分のリアリティがあるって感じですか?「こういうのが大変だったんだろうな」みたいな。
業天:それもありますし、あるいはやっぱりこういう粗利率の見せ方にもなるなとかは思いました。
手嶋:資料で注目したいのが、10ページ。オンプレミスの物理鍵や電子キーをクラウド型に切り替えてますということで、実は家庭向けにも事業を始めていて。法人向けだけではなく、MIWA Akerun Technologies、国内最大手の錠前メーカーと合弁会社を作って、個人向けの市場も開拓しつつあると。
セーフィーも通常のカメラをリプレイスしていく市場が大きいと見ていましたが、Akerunにも似たような要素があるんですかね?
業天:そうですね。スライドの資料の表現が面白いですよね、オンプレミス型とか。あと、切り替え先の業界は電子錠だと思っていたんですけど、オンプレミス型の特徴として「警備の駆けつけ」とかって書いてあるので、この資料の中に。これはセコム・アルソックなんですかね、仮想敵は。
手嶋:なので、多分単なる鍵というよりは大きい市場を見ていそうだなという感じがありますね。11ページで顧客基盤が載っているので見ると、いわゆるスタートアップが書いたような…こういう資料なのであえてそうしたのかもしれないですが、有数の大企業がバーッと入っていると。NTTドコモとか、三井不動産、ニコン、野村不動産、博報堂がクライアントで使っているんですね。
13ページは、技術的な競合優位性と差別化について触れられています。単なるソフトウェア技術だけでなく、セキュリティや無線通信などIoTならではの技術要素にノウハウと実績の蓄積があるよと。Stroboもここら辺は技術資産として蓄積している感じですよね?
業天:まさにこの2点は蓄積している部分ですね。Stroboも「工事不要」を訴求している中で、無線通信はやはりすごく重要な技術なんです。きちんと繋がる状態で提供するというのが実はかなり難しいことなんですよね。それができずに撤退していった会社も結構いますし。なのでたしかに強みとしてはしっかりと訴求できるポイントだと感じます。
手嶋:これはいわゆるソフトウェアエンジニアとは全く違う人たちって感じですよね。ここら辺の技術者の人って。
業天:全く違う人たちですね。
手嶋:そういう人たちを採用していかなければならない事業なんですね。
業天:あとこの13ページでは、左下の2番目の他社との比較ポイントが気になりました。「ブロックチェーン等の未成熟技術はハイリスクになることも」という箇所。これは競合をかなり意識したワーディングではないかと。
手嶋:競合でいくと、ビットキーとかがこういうことをやってるんですか?
業天:ビットキーは今はそんなにやってないかもしれないですが、「ブロックチェーン×スマートロック」を押し出されていた時期もありましたね。僕はビットキーが押し出されていた背景を知らなかったので、すごく唐突感があるなと思ったんですけど。
手嶋:ブロックチェーンでやらないだろうと思って見ていたんですけど、実際そういう例があったということですね。
業天:そうですね。やっぱり近すぎる業界の資料って、気付く点が多くて面白いですよね。
# 地方展開、住宅市場参入——フォトシンスのマーケットポテンシャル
手嶋:14ページは、プラットフォームとしてのAkerunについて。入退室情報を起点としてるので、人事労務ソフトやジムなどの予約管理システムと連動できますよと。
続いて、16ページはマーケットポテンシャルについて。これはセーフィー以上に大きなマーケット規模があるという。セーフィーは台数でしたが、フォトシンスは金額で表しています。TAMが6.4兆円だということで、これはどういう定義なんですかね?
業天: 6.4兆円の内訳が書いてありますね。法人向けだと、月額1.8万円×12ヶ月が前提で、個人向けが月額2500円×12ヶ月だと。かつ、個人だと普及率が100%前提なので、TAMってやっぱりそういうものなんですかね。投資家目線ではどうですか?
手嶋:そういうものじゃないですかね。極限まで拡大解釈するところですと。「加速するシェアリングエコノミーとDX化の流れの中で拡大するマーケット」とあります。シェアリングエコノミーは、いろいろな人が一つの場所を共有するみたいな中で使われるってことなんですかね、Akerun自体が。
業天:ですかね。私もオフィスにスマートロックを入れてるんですけど、便利ですよね。シェアオフィスではありませんが、やっぱりいろいろな人が出入りするので。
手嶋:続いて、18ページに記載されているのは成長モデル。顧客セグメントをSMBから大企業に広げていくのと、エリアも東京から地方展開をしていくと。それから、セーフィーと同じくパートナーモデルを推進したいと書かれていますね。クロスセルも、いろいろなソリューションを開発予定のようです。
僕は19ページに注目したんですけど、2020年から2021年までめっちゃ人増えてるんですよね。1年で111人から186人ですよ。これって、普通に考えて組織が混乱するぐらいの人数拡大ですよね。
業天:すごいですよね。
手嶋:地方拠点のことも書いてありますね。
業天:あとは、資本業務提携をしている企業が多いじゃないですか。セーフィーのようにパートナーセールスをあまり押し出してはいないものの、2021年はそのチャネルが結構動き出すに伴って、カスタマーサクセスやパートナーサクセスのポジションも増えてくるとかなんですかね。
手嶋:明確にアクセルを踏んでますよね。僕はそう感じました。あと25ページでTAMで重要なのが、住宅など居住空間への広がりだと書かれています。業天さんから見て、スマートロックのサービスは住宅市場に広がりそうですか?
業天:ここはなんとも言えないですね。
手嶋:さすがに自前で営業するのは厳しいから、ジョイントベンチャーで参入したんですかね。
業天:そうですね。美和は鍵メーカーですが、同様に家の建築過程に入り込んでいる企業との提携を進めていくと思います。でも、新築の戸数って意外に多くはないじゃないですか。なので短期的にはちょっとわからないですよね。
手嶋:そうですね。長期的には大きいマーケットと捉えて、明確にやっていきそうな感じですよね。29ページにARRの推移が載っていて、たしかにここ1年だけの数字で見ると、人が増えているペースに比べてそんなに積み上がってる感じはしませんよね。ここから時間差で結果が出てくる可能性があるんでしょうか?
業天:そこはなんともですけど。でも事業者目線では、綺麗に伸びてますよね。
手嶋:しっかり積み上がってきてると。
業天: IoT界隈の中でいうと、やっぱりSaaSに転換が必要な企業は多いと思うんですけど、そこを綺麗に転換していってちゃんと伸びているのはすごいですよね。
手嶋:Akerunも最初はリカーリングモデルじゃなかったんですか?
業天:そうですね。最初は家庭向けに3〜4万円で鍵を販売するところからスタートしています。そこから切り替わっていったのがまたすごいところですね。
手嶋:セーフィーとフォトシンス、株式市場の評価は二極化している会社ですけど。冒頭にあった通り、同じ時期に創業して、同じ時期にIPOした点でいくと、そういう流れのタイミングなのかなと思いました。それに少なくとも参入障壁がめちゃくちゃ高いですよね。もはやスマートロックも。
業天:高いですね。
手嶋:ですよね。シェアは書かれていませんが、成長はしていくのではないかと思いました。ここまでは、業天プロに起業家目線で最近上場したセーフィーとフォトシンスの2社について語っていただきました。
前半はここまでです。後半は、業天氏が設立した「strobo」の挑戦について伺っていますので是非ご覧ください。