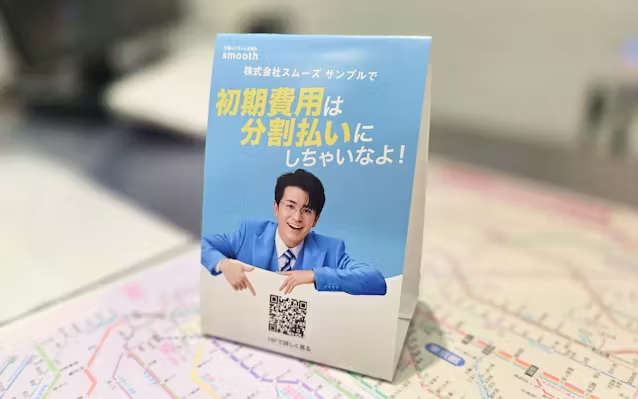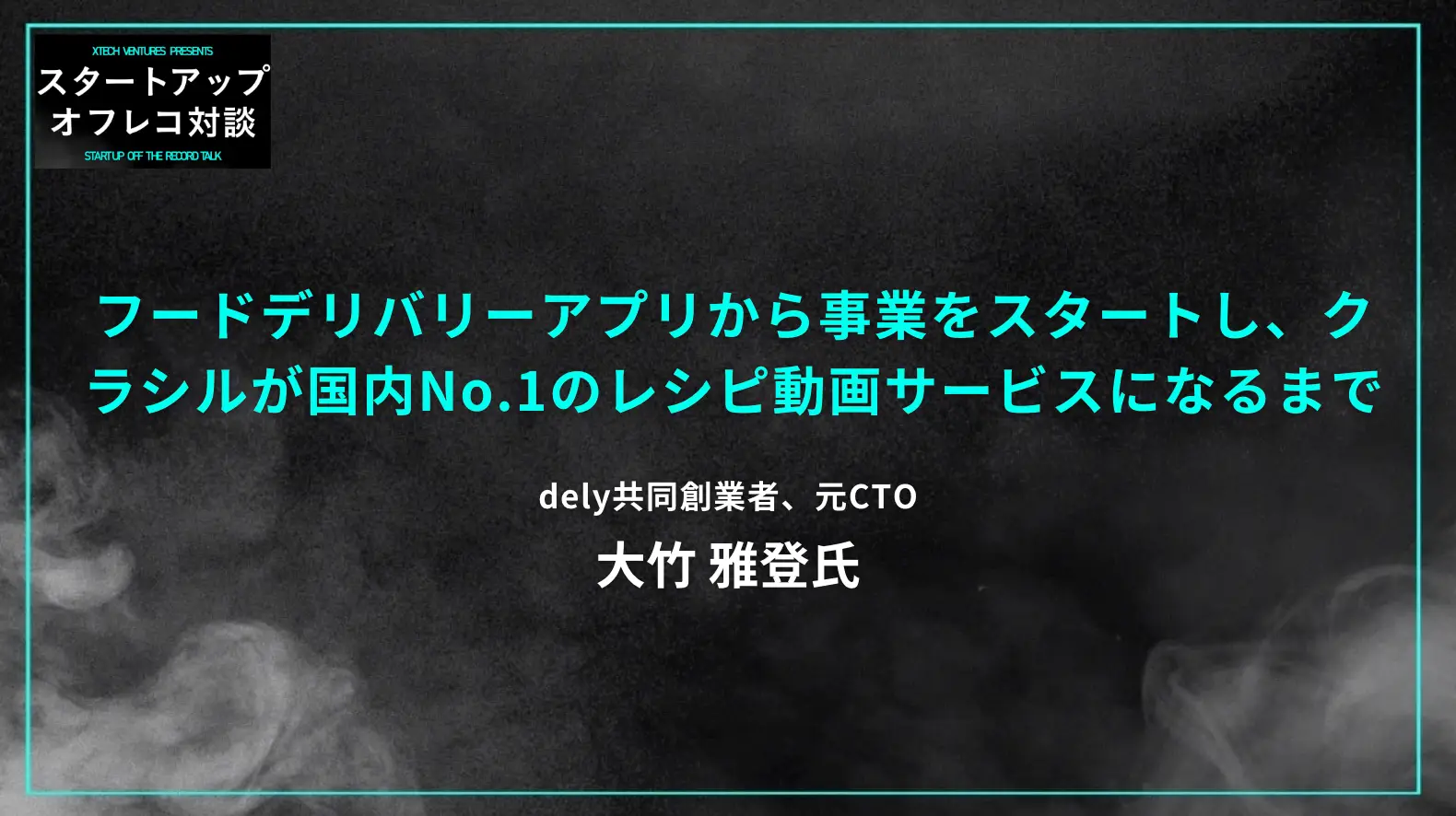#14 「資金1000万円未満」から始まった世紀のピボット、マネックスグループへのM&Aの裏側ー コインチェック 大塚雄介氏
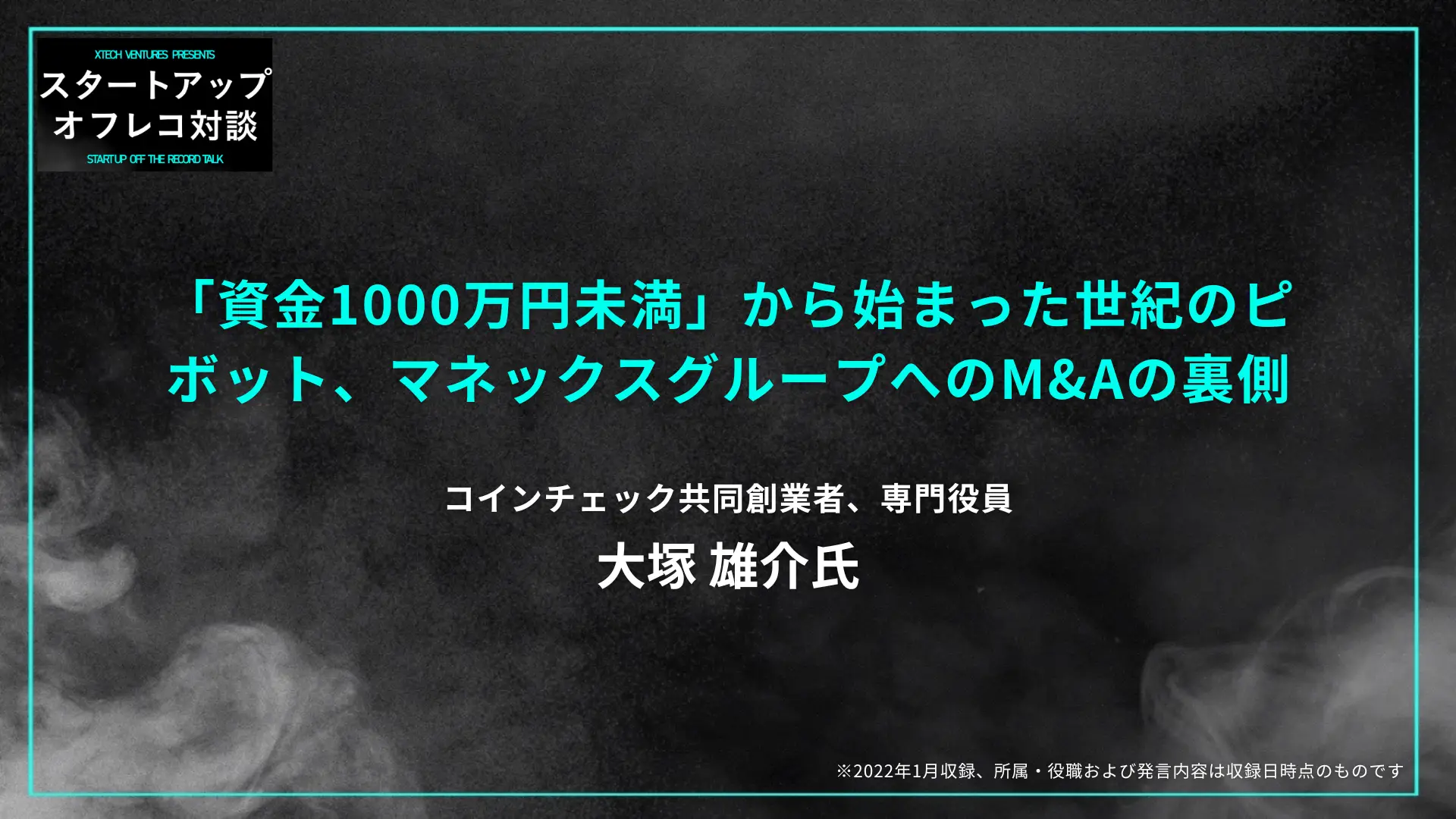
「スタートアップ オフレコ対談」は、XTech Venturesの代表手嶋とゲストの方をお呼びして対談する番組です。今回はSTORYS.JPというユーザー投稿型のメディアから大ピボット、そしてマネックスグループへの参画を通じて、現在国内の主要な暗号資産取引所となっているコインチェックの大塚雄介さんをゲストにお迎えします。
前編では、STORYS.JPというユーザー投稿型のメディアから大ピボットの裏側、M&A後に企業文化の全く異なる中で、どのような困難があったのか。そして現在取り組んでいる新規事業、日本初のIEO、突如沸きたったWeb3ムーブメントのきっかけについて聞きました。
スピーカー
・大塚 雄介氏(@yusuke_56)
コインチェック共同創業者、専門役員
・手嶋 浩己(@tessy11)
XTech Ventures代表パートナー
目次
# 「権威ではなく役割」柔軟性を重視する組織運営
# 「資金1000万円未満」から始まった日本テック業界史上最大のピボット
# 「3つの軸」で見極めた暗号資産という新大陸
# 「危機を機会に」マネックス傘下での華麗なる復活劇
# 「2年間の金融庁との対話」で築いた日本初IEOの独占市場
# 「予想を超えた爆発」 NFTバブルとの格闘
# 2021年末から到来したWeb3ブーム
※音声収録日:2022年1月収録
※スピーカーの所属および役職ならびに記事中の発言内容は収録日時点のものです。
「権威ではなく役割」柔軟性を重視する組織運営
手嶋:XTech Venturesのスタートアップオフレコ対談をやっていきたいなと思います。今日のゲストは、(2020年の)年末に本を出された、まさに"時"の人です。コインチェックの大塚さんに来ていただいて、コインチェック自体やWeb3、NFTアーティストとしての大塚さんの活動について聞いていきたいと思います。大塚さん、こんにちは。
大塚:こんにちは。よろしくお願いします。
手嶋:お願いします。では、おおまかには対談の前半はこれまでのお話、後半は今後の話を聞かせてください。まず、これを聞いている方のほとんどは大塚さんのことを知っていると思うのですが、ざっくばらんに自己紹介と、今コインチェックでどういう役割(ロール)を担っているのか、そのあたりを教えていただけますか?
大塚:コインチェックの大塚と申します。役職は執行役員です。担当領域としては、CMなどを手掛けるマーケティング部、お客様からのお問い合わせに対応するカスタマーサポートの部署、それから広報の部署を見ています。これらが暗号資産取引サービスCoincheckについて担当している役割です。
これ以外に、Sharely(シェアリー)という新規事業の担当もしていますので、新規事業開発もやっています。
手嶋:一時、専門役員になられて、その後もう一度執行役員に戻られていましたが、それは会社内での幹部全体の役割分担を、毎年柔軟に変えているということなのでしょうか?
大塚:そうですね。基本的にコインチェックでは、役割(ロール)というのは権威ではなく、あくまで仕事上の役割分担だと考えているので、かなり柔軟に変えています。
私が専門役員になった時は、コインチェックのフェーズが変わったタイミングでした。それまで私と(共同創業者の)和田が何でもかんでも創業から全部やっていたのですが、このやり方を続けるのは事業をスケールするためには良くないよね、という考えもありました。そこで、私と和田は一度事業のすべてから手を離し、新規事業にリソースを全部投入して、私たちがいない中でどうなるかを試した時期でした。
手嶋:なるほど。その試みがうまくいったので、また役割(ロール)を再配置したという感じですか。
大塚:はい、私たちからの知見やノウハウの共有(ナレッジデリバリー)ができた状況になりました。ただ、2020年以降、また事業と会社がぐっとスケールできる局面が見えてきたので、私たちがよりコミットしていく方が事業の成長スピードを上げられるのではないか、という判断があり、私がまた事業の中に入ってやっている、という流れです。
手嶋:今、Sharely以外の事業も含めて、もう一度関わり始めているという感じですね。
大塚:そうですね。
「資金1000万円未満」から始まった日本テック業界史上最大のピボット
手嶋:分かりました。そもそも大塚さんがコインチェック、旧レジュプレスに入社された時は、まだ暗号資産ではない別の事業をやっていた時期ですよね。
大塚:はい、まだ「STORYS.JP(ストーリーズドットジェイピー)」というサービスも世に出ていなくて、どういうコンセプトでやっていこうかと言うことを社内で話していた時期ですね。
手嶋:そこから、日本のテクノロジー史の中でも世紀のピボットの大成功例だと思うのですが、ピボットで暗号資産取引所に至るまでの思考の変遷はどのようなものだったのでしょうか?
大塚:そこは私と和田の中ではクリアでして、もともと「STORYS.JP」をやっていたのですが、これは当時出てきていたTwitterやFacebookの延長線上で、もう少し長い文章を書くサービスが来るのではないか、という考えで始めました。これを2年間ぐらいやったのですが、当時、和田は22歳くらいの学生で、私も起業経験など全くない状態で、「とりあえずやってみた」というのが大きいんです。
それはそれでやり切ったのですが、一定の線形の成長は見えながらも、他のスタートアップを見ていると学ぶことが非常に多くありました。アプローチの仕方を、今あるものの延長ではなく、未来から逆算して考えたほうがいいね、と和田と話をしていました。
「STORYS.JP」をやり切り、成長の角度がある程度見えてきたところで、もっと角度を上げるためにどうすればいいかと考え、違う事業を検討し始めました。
「3つの軸」で見極めた暗号資産という新大陸
手嶋:より急成長する事業をやりたい、というスタートアップとしてすごく健全な衝動ですよね。2014年に暗号資産の取引所をやろう、となったわけですが、そこに至った経緯はどんな感じだったのでしょうか。
大塚:まず、次の事業のポイントとして、私と和田の中で3つの共通認識がありました。1つ目は「全く新しい技術革新が生まれる領域」であること。これがブロックチェーンでした。
2つ目は「ユーザーインターフェースが大きく変わる」こと。携帯からスマートフォンに変わった時にLINEのようなアプリが急成長したように、お金を送るインターフェースも変わるのではないかと思いました。
3つ目は「法律がなかったところに新しくできる、または緩和される」こと。当時、自民党が暗号資産を「価値記録」として整理する見解を出し、これを潰すのではなく育てていこうという方向性が見えたので、法律も変わっていくだろうと。
この3つの軸が交差するところに新しい事業があるだろうと考えていました。当時、日本よりもビジネスが先行して興ることが多いアメリカでは(暗号資産取引を提供する)Coinbaseがトピックになっていて、どうも暗号資産は盛り上がりそうだ、と。一方で、日本の状況を見ると、FX(外国為替証拠金取引)の市場が一定存在すること、暗号資産取引ではMt.Gox(マウントゴックス)という取引所があって、すごく盛り上がったけれど問題があって破綻した、という出来事もありました。なので、新規参入できる可能性があるのかな、と。
私たちは最後発で、すでにbitFlyerさんや現在のZaifさんなどが存在していましたが、自分たちが「STORYS.JP」で培ってきた「使いやすいプロダクトを出す」という強みがあれば、参入角度次第で勝ち抜けるのではないか、という仮説を持っていました。
手嶋:「STORYS.JP」は最終的には譲渡されましたよね。それは当初から考えていたのですか?
大塚:いえ、追加で新規事業を始めよう、という感じでした。私と和田のリソースをどこに割くかの話になった時に、「STORYS.JP」の成長速度よりも、新しい事業で成長速度を上げていった方がいいのではないか、という選択をしました。
先ほどの専門役員の話と近しいですが、暗号資産事業をやる時は、「STORYS.JP」からは完全に手を引いて、他のメンバーに運営を任せていたんです。
手嶋:その時点で社内の人数は何人ぐらいで、キャッシュはどれくらいあったのですか?
大塚:社員はフルコミットしていたのが和田だけで、あとはインターンと、私のような……雇われてもいないのに無給で関わっている感じでしたね。3,000万円調達した事業運営のための資金も1,000万円を切っていたんじゃないかなと。
手嶋:当時、深く考えすぎていたらアクションができなかったかもしれないですね。
大塚:そうですね。そういう意味ではリスクが取りやすかった。私は他の会社で働いていましたし、和田も当時23歳で、別にそこで全てがなくなっても人生は困らないだろう、と。今の状況とは全然違いますね。
手嶋:世紀の大ピボットはそういう状況で行われたんですね。
大塚:投資家の皆さんにも一切言わずに勝手にやってしまったので、あまり見習うべきことではないかもしれないです(笑)。
手嶋:まあ、でも勝手にやって勝手に成功してくれるのが一番いい、という考え方もありますからね。
「危機を機会に」マネックス傘下での華麗なる復活劇
手嶋:そこから数年で時代の波も来て、後発ながら取引所の中で1位、2位を争う規模になり、そして皆さんご存知の通り、事件もありました。マネックスグループに入られたのは2018年ですね。
大塚:はい、2018年です。
手嶋:マネックスグループに入られてから今に至るまでを、フェーズ分けするとしたら、どのようになりますか?
大塚:大きく3つだと思います。1つ目は、まず「登録業者になるまでのフェーズ」。私たちは金融庁に登録をしなければ事業ができませんので、そこを一番のマイルストーンとしていました。
2つ目のフェーズは「PMI(Post Merger Integration)のフェーズ」。コインチェックのカルチャーと金融のカルチャーをいかに融合させていくか。これは非常に大変でした。
そして最後の3つ目は、その融合がある程度終わり、お互いの理解が深まって、市場も盛り上がってきた中で、きちんと「事業を拡大していくフェーズ」。この大きく3つのフェーズに分けられるかなと思います。
手嶋:それぞれのフェーズで大変だったことは何ですか?
大塚:1つ目の登録フェーズでは、登録を完了するまで新しいことが一切できなくなってしまうことでした。それまでのコインチェックは、新しいことをどんどんやって成長してきた会社です。それを全部止めて、ひたすらガバナンスやコンプライアンスを固めていく。
そうなると、その必要性を理解できる人と、「自分たちはこういうことをやるために来たわけじゃない」と感じる人が出てきてしまい、会社のベクトルを合わせ、皆に方向性を理解してもらうのが大変でした。
手嶋:その時、和田さんと大塚さんは主に何をされていたのですか?
大塚:(コインチェック社内の)組織を奮い立たせる役割もありますし、一方でマネックスグループと今後どういう形でやっていくか、お互いを理解し合うことも大切でした。特に私はマネックスとコインチェックの間に入ってコミュニケーションするような役割で、和田はそういうタイプではないので、今まで通りプロダクトを作っていく、という役割分担でしたね。
手嶋:そして免許が取れて、晴れてもう一度事業を伸ばそうという第2フェーズ、PMIのプロセスでは何が大変でしたか?
大塚:そうですね、例えば、コインチェックはもともと社内コミュニケーションはすべてチャットツールで、ドキュメントを残し、テキストコミュニケーションがメインの文化でした。一方、金融業界で長くキャリアを積んできた方々は、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが当たり前。どちらも正しいことなのですが、仕事の進め方の違いをお互いに理解し合いながら進めていくのは、一定の大変さがありました。
手嶋:和田さんは尖った経営者というイメージですが、PMIのプロセスにはどう関わっていたのでしょうか?
大塚:当初は私がマネックスとコインチェックの間に入っていましたが、そうするとだんだんメンバーから「大塚はマネックス側の人間だ」と見えてきてしまうんです。これは人の心理として仕方ない。一方で、和田はずっと今まで通りやっているので、「和田さんはコインチェック側の人だよね」という形で人心が集まっていました。なので、途中からは私が専門役員としてあえて執行側の役員から降りて、和田が先頭に立って、KPIを決めてエンゲージメントを高めていく、ということをやっていきました。これは結構大きかったと思います。
手嶋:和田さんもその時期に経営者としての幅を広げていった、という感じですね。
大塚:そう思います。
手嶋:マネックスグループに入ってプラスだったことでいうと、当然、与信や金融業界的なカルチャーのインプットがあったと思いますが、細かいレベルではどういう点がプラスでしたか?
大塚:一番はやはり人材ですね。例えば、今の法務担当の執行役員は、弁護士資格を持ちながらトレーダー経験もあるという、法務もビジネスも分かる方なのですが、そういう人材はスタートアップではまず採用できません。今の社外取締役の先生方もそうですし、そういった方々の力を借りられるようになったのは非常に大きいです。
手嶋:今、マネックスからの出向者の方は多いのですか?
大塚:今は出向者はほぼいないんです。マネックスグループに入った直後の大変な時期には助けていただきましたが、再建していくうちに新しく採用したメンバーも増え、今はほぼ自分たちだけでやっている、という感じです。
手嶋:コインチェックは世紀のピボット例であり、マネックスグループへのジョインは世紀のM&Aの成功例になりつつあるのではないかと、和田さん、大塚さん、マネックスグループの成し遂げたことに客観的に尊敬しています。さて、現在のフェーズですが、暗号資産事業はマネックスグループの一番の稼ぎ頭になるなど、期待感は年々上がってきている感じですか?
大塚:私から言いにくいところもありますが、非常に期待していただいています。これは私たちだけでなく市場全体が広がっていることもありますので、その期待に応えるべく、マネックスグループのメインストリームとしてやっていく大変さも感じながら取り組んでいます。
手嶋:グループ内での交流やシナジー創出といった発想はあるのでしょうか?
大塚:基本的には独立独歩でやらせてもらいつつ、月に一度グループの役員定例があったり、米国で証券事業とクリプトにも取り組んでいるトレードステーションのチームと交流したり、お互いのマーケティング手法についてセッションしたり、といった知見の交換は行っています。
「2年間の金融庁との対話」で築いた日本初IEOの独占市場
手嶋:次に新規事業についてです。IEO(Initial Exchange Offering)の事業を昨年から始められていますね。これはコインチェックの取引所に暗号資産を上場するサービス、という理解でいいですか?
大塚:そうですね。
手嶋:実績は今のところ1件で、パレットトークン(PLT)がIEOで上場した通貨ですよね。このIEO事業は、今日本でやっているのはコインチェックだけですか?
大塚:はい、そうです。
手嶋:なぜコインチェックしかまだやっていないのでしょうか?
大塚:これは、日本のIEOに関するレギュレーションを、私たちが2年間かけて金融庁などと対話を続けながら作ってきた、という経緯があります。税務上や会計上どう扱うかなど、開発だけでなく全社一丸で取り組む必要があり、立ち上げが非常に大変なので、他社さんがリソースを割きにくい、という事情があるのかなと思います。
手嶋:実現したのが1件、既に発表されていて準備中のものが1件ありますが、引き合いはもっとたくさん来ているんですよね?
大塚:はい、ありがたいことに、ものすごい数の問い合わせをいただいています。少し順番待ちになってしまっている状況です。
手嶋:(順番待ちになってしまっているのは)審査が大変だからなのでしょうか?
大塚:審査もですが、それ以上に、発行体側、つまりトークンを発行する企業側に、トークンに関する様々な論点を理解していただくのが大きいですね。発行したトークンを自社でどう会計処理するのかを監査法人と詰めたり、税務上の扱いを整理したり、そういったサポートがかなり大変です。
手嶋:なるほど。暗号資産について詳しく、準備ができている会社だけがIEOをやろうとしているということではないんですね。
大塚:濃淡があります。IEOは資金調達ではありますが、それは一側面でしかなく、発行したトークンがコミュニティでどう使われるか、というプロダクト設計が重要です。
ですから、何でもかんでもIEOができるわけではありません。1件目のパレットトークンもそうですが、2件目として発表しているフィナンシェさんも、きちんとプロダクトがあり、コミュニティの中でトークンが使われる設計思想があったことが大きいです。
手嶋:IEOで上場した後、コインチェックは株式市場の取引所のように、開示情報などをモニタリングする役割も担っているのですか?
大塚:はい、やっています。財務状況は大丈夫か、開示体制は整っているか、などを継続的に見ていきます。ですから、最近はIPOを目指している企業がIEOを選択するケースもありますが、既存の株主への説明など、クリアすべき課題は多く、簡単に資金調達できる魔法の杖ではない、と理解してもらう必要があります。
手嶋:今後の理想的なペースはありますか?
大塚:年に何件か、という理想はありつつも、数を出せばいいという話ではなく、クオリティが下がっては意味がない。特に最初のうちは、ここで市場が躓いてしまわないように、慎重に進めていきたいと考えています。
「予想を超えた爆発」 NFTバブルとの格闘
手嶋:もう一つの新規事業、NFTマーケットプレイスについても伺います。これはいつ始められたのですか?
大塚:2021年3月ですね。
手嶋:どうですか、手応えは。当初想定していたよりもマーケットが盛り上がっている感じでしょうか?
大塚:そうですね。社内でもよく話すのですが、「NFTをやろう」と言っていた頃には、こんな状況になるとは全く思っていなかった、というくらい盛り上がっています。
手嶋:その盛り上がりに追いつくために取り組んでいることは何ですか?
大塚:ひたすら採用です。開発者も必要ですし、IPホルダーなどと交渉するビジネスディベロップメント(ビズデブ)、そしてプロジェクト全体を動かすプロジェクトマネージャー(PM)。この3職種の人材が特に必要になっています。
手嶋:競合であるOpenSeaは、なぜあれほど巨大化したのでしょうか?
大塚:黎明期に「NFTクジラ」と呼ばれるような、イーサリアムを大量に保有している初期からのプレイヤーたちがいて、彼らが市場を支え、買い支えていたのが大きいのかもしれません。あとは、やり続けた、ということでしょうか。
2021年末から到来したWeb3ブーム
手嶋:2020年の11月頃から突然「Web3」ブームが来ましたよね。あれは何がきっかけだったのでしょうか?
大塚:もともと「Web3」という言葉自体は、Polkadotの創設者であるギャビン・ウッドが提唱したもので、界隈では以前から使われていました。ただ、確かに去年の冬ぐらいから、日本の特にVCの方々が盛んに言い出して、何かあったのかな、と。
手嶋:もしかしたら、Axie Infinity(の価格)がすごく跳ねたあたりから、GameFiの流れがWeb3という言葉にシフトした感じもしますね。
最近では、Polkadot上でAstar Networkを開発されている渡辺創太さんが注目されていますが、あれは客観的に見て良いポジションにつけているプロダクトなのでしょうか?
大塚:そうですね。彼はもう2年ぐらい前から知っていますが、細かくピボットしながら今の立ち位置を築いていて、良いポジションにいると思います。プロダクトをきちんと作っていますし、Astarを保有するとステーキング報酬がもらえるなど、クリプトの特性をよく理解したエコシステムの設計がされているなと感じます。
手嶋:私も最近ようやくWeb3ムーブメントに乗ろうと勉強して、彼らが2018年からそういうことをやっていたのだと理解しました。すごいですよね。
では、前半戦はここまでとさせていただきます。後半戦は、今後の話を伺っていきたいと思います。大塚さん、ありがとうございました。
大塚:ありがとうございました。
前半はここまでです。後半は、大塚氏のNFTアーティストとしての活動、クリプト産業の未来について伺いますので是非ご覧ください。