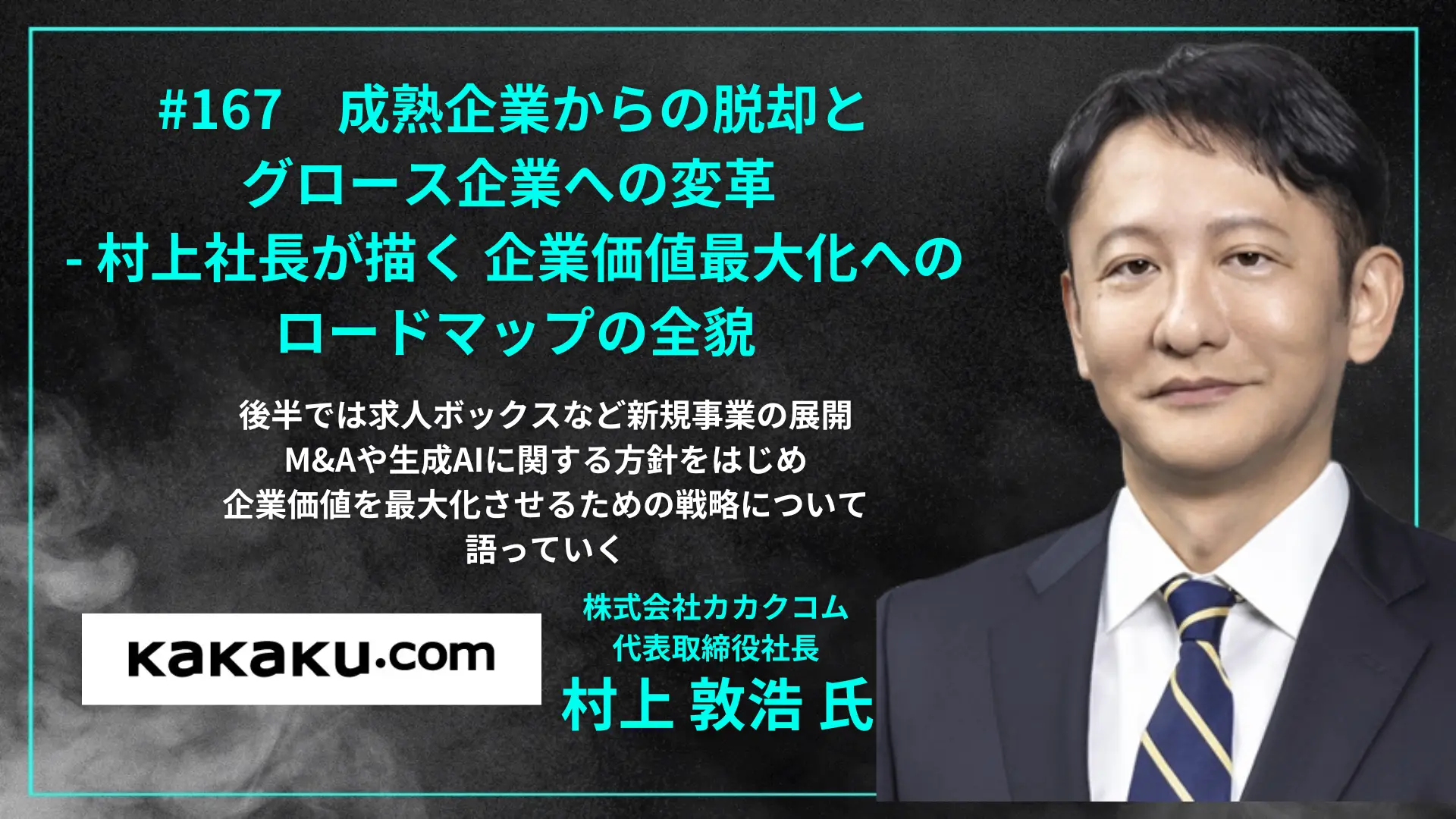有機合成の研究者から、技術と経営の橋渡しへ。技術への投資とキャリアの掛け算

「良い技術」は、どうすれば「成功するビジネス」になるのか。大学院で有機合成を研究し、メーカーで創薬支援に携わった荻野公平は、研究開発の現場で「技術とビジネスの断絶」を痛感しました。その課題意識を胸に、コンサルタントを経てベンチャーキャピタリストの道を選んだ彼が、新たな舞台としてXTech Venturesを選んだ理由とは。
コニカミノルタ時代に得た数千億円規模の事業撤退の教訓、技術系スタートアップに向き合う独自の視点、そしてXTech Venturesならではの投資スタイルまで。彼のキャリアを貫く「技術と経営の橋渡し」への思いに迫ります。
2017年埼玉大学を卒業後、東京大学大学院に進学し創薬科学の研究に従事。2019年大学院卒業後、コニカミノルタ株式会社に入社し、 ヘルスケア領域における研究開発(がん細胞のイメージング)や新規事業立案等を担当。その後、2021年よりPwCコンサルティング Strategy&にて戦略コンサルティングに従事し、ヘルスケアを中心に、テック、通信、広告業界等の企業に対し、経営戦略・事業戦略の策定や変革の実行を支援。2024年6月XTech Venturesに参画。
「良い技術」がなぜビジネスで負けるのか? 研究者がVCになるまでの軌跡
─まず、これまでのキャリアについて教えてください。新卒でコニカミノルタに入社されていますが、どのような理由だったのでしょうか?
荻野:大学院の修士課程を卒業してコニカミノルタに入社しました。もともとは博士課程まで進学し、製薬会社に入ろうと考えていたんです。しかし、大学院2年生の夏頃に家庭の事情で就職する必要が出てきました 。その時期に募集していたのがコニカミノルタで、希望していた製薬会社ではなかったものの、ちょうど「創薬支援事業」に力を入れるという方針を打ち出していて。ここであれば自分の関心と近いと考え、応募したという経緯です。
─大学院ではどのような研究をされていたのでしょうか?
荻野:大学院では「有機合成」という化学の研究をしていました 。非常に小さな分子のレベルで、新しい化学物質を作るという研究です。特に私の場合は、有機合成の手法を用いて新しい「薬」を作るというテーマで研究を行っていました。
コニカミノルタでも、創薬支援に関連する研究開発に従事しており、具体的には、がん細胞に色をつけ、そのがん細胞がどこにあるかを判別する、診断のような領域の研究に取り組んでいました。印象に残っているのは、当時の研究環境です。周りの研究者の方々のレベルが非常に高く、私がいた研究チームは半分以上が博士号持ち、中にはアカデミアから転職してきた人もいて、研究レベルではかなり良い結果が次々と出ていました。
しかし、それらの良い研究結果をいざ事業化しようとして、お客様の候補となる企業などに持っていくと、なかなか上手く進まないという経験を多くしました。研究自体は非常に良いのに、それがうまくビジネスにつながらない、という状況は、当時かなり印象に残った出来事でしたね。この時の経験が、VCの道に進むことにもつながっている感覚があります。
─そこから、コンサル業界という異なる業界に転職されています。
荻野:コンサルティング業界には3年ほど在籍し、主に製造業や製薬会社などのプロジェクトに携わりました 。転職の理由は、まさにコニカミノルタでの経験がきっかけです 。研究は良いのに、うまくビジネスに結びつかない状況を見て、「研究者が良い研究をしているだけでは、なかなかビジネスにならないのではないか」と感じました。
当時の私としては、「技術が分かり、かつ経営も分かる人」がいないと、うまく事業化できないんじゃないか、と安直ですが思ったんです。自分はもともと研究者だったので、少し経営側にキャリアを移すことで、技術と経営の「橋渡し」ができるのではないかと考えました。そこで、経営的な仕事に携わりたいと思い、コンサル業界へ転職したんです。せっかくやるなら戦略レベルで技術との橋渡しがしたいと思い、戦略コンサルに決めました。
─新卒で技術、次のキャリアでビジネスサイドを経験されたのですね。そこから、ベンチャーキャピタル(VC)という仕事には、どのような経緯で興味を持ったのでしょうか?
荻野:もともと「技術と経営の橋渡し」をしたいと思ってコンサルティング業界に入ったのですが、実際に働いてみると、そういうプロジェクトに携われる機会はあまり多くなくて。
どちらかというと、中期経営計画の策定支援や、新規事業やM&Aの戦略検討など、かなりハイレイヤーの仕事が多く(戦略コンサルなので当たり前なんですが...)、技術をうまく事業化するようなプロジェクトには、あまり携われませんでした。ビジネスの基礎スキルを徹底的に鍛えてもらい、凄く恵まれた環境だったので充実した日々を過ごしていたものの、このままでいいのかと感じていました。その時に、「これ(技術と経営の橋渡し)は、ベンチャーキャピタルに行ったらもっとできるのではないか」とふと思い、VC業界について調べ始めたのが興味を持ったきっかけです。

「シードが本質」。GPの言葉に惹かれ選んだXTech Venturesでのキャリア
─数あるVCの中から、XTech Venturesを次のキャリアの舞台として選ばれた最大の理由は何でしたか?
荻野:VC業界を調べ始めた当初からXTech Venturesを知っていたわけではなく、インターネットで調べていた時に偶然見つけ、問い合わせフォームから応募しました。
最終的にXTech Venturesに決めた理由はいくつかあります。まず、キャピタリストの皆さんやGPの手嶋、西條と話をさせてもらった際、非常に「話しやすかった」ことです。
また、手嶋と話した時に印象的だったのが、「ベンチャーキャピタルの投資は、シードに投資するのが本質だと思っている」と話してくれたことです 。シード投資ではどこのVCもまだ投資していない会社に投資するという事であり、ソーシング方法や意思決定において、他のステージの投資とは明確に異なるという事です。XTech Venturesが「シード」というステージに誇りを持って取り組んでいることに強く惹かれました 。
もう一人のGPである西條からは、これまで未経験の方をキャピタリストとして採用し、自走したり独立したりする方を多く輩出してきたという話を聞きました。未経験の人をいかに活躍させるか、そのノウハウを持っているという点にも魅力を感じ、ここで働きたいと思いました 。投資領域に関しても、手嶋から「好きに何でもやっていいよ」と言われたので、逆に「なんでもできるんだ」とポジティブに捉え、入社を決めました。
─西條さんや手嶋さんをはじめ、XTech Venturesのチームメンバーの皆様と働く中で、どのような点に魅力を感じますか?
荻野:やはり、皆さん非常に話しやすい雰囲気があることです。その上でGPの手嶋や西條からは、メンバーの自主性を尊重してくれる魅力を感じます。「自由にやっていいよ」という言葉通り、かなり自由にやらせてもらっていると感じています。
実際にこれまでXTVではIT/ソフトウェア領域への投資がメインだったのですが、私の入社を期に、大学発ベンチャー等のいわゆるディープテックの領域への投資もさせてもらっています。本当にここまで自由にやらせてもらっていいのかと最初は思いましたが、その分なんとしてもファンドとしてこの新しい領域で結果を出さねばと思い頑張っています。
─入社前に抱いていたイメージと、実際に入社してから感じた良い意味でのギャップがあれば教えてください。
荻野:前職がコンサルティングファームだったので、特に強く感じるギャップですが、前職では何かアクションを起こすにしても、常に入念な調査を行ってから実行するという考え方でした。一方、XTech Venturesに入社してからは、とにかく「決断のスピード」が速いことに驚きました 。調査をしながら同時に決断していく、というような感覚です。1日にいくつもの意思決定が行われており、これは非常に良い意味でのギャップでしたね。

投資先の「うまくいった」が最高の報酬。伴走者として走り続ける日々
─現在の「インベストメントマネージャー」という役割、また具体的な業務内容を教えていただけますでしょうか。
荻野:私は入社時「アソシエイト」としてスタートし、1年後に「インベストメントマネージャー」になりました 。XTech Venturesのキャリアパスはアソシエイト、インベストメントマネージャー、プリンシパルと進みますが、根本的な業務内容自体はアソシエイトの時から大きくは変わっていません 。
投資先のソーシング(発掘)、デューデリジェンス(投資調査)、投資実行、投資後の支援、さらにはファンドレイズやLP(投資家)の皆様とのやり取りなど、VC業務の川上から川下まで全てをアソシエイトの段階から担当します 。
インベストメントマネージャーとしては、これら一連の業務をより高いクオリティで実行することが求められます。加えて、アソシエイトのフォローといった役割も担うようになります 。
─コニカミノルタでの研究開発、コンサルティングファームでの経験は、現在のベンチャーキャピタリストとしての業務にどのように活かされていると感じますか?
荻野:一番大きいのは、コニカミノルタ時代の経験ですね 。私が関わっていた創薬支援事業や有機ELの事業では、会社として大型M&Aも含めてそれぞれ数千億円規模の投資をしていました 。どちらの事業も、技術開発自体はうまくいっていた側面もありましたが、ニーズが不確かなまま進んでしまった部分がありました。
実際に製品を作ってみたら、想定していたニーズがあまりないということが分かり、結果として事業はうまくいかず、現在はほとんど撤退しています。
この「技術が良くても、本当にニーズがあるのか」という視点を突き詰めずに進んでしまった経験は、自分の中で非常に強く残っています。そのため、現在の投資活動、特に大学発のベンチャーや技術ドリブンな会社を検討する際には、「本当にニーズがある技術なのか」という点をかなり意識しています。
当時特に感じたこととして、「いろんなものに応用できる技術」というのは、しっかり紐解くと「何にも応用できない技術」である可能性もある、ということ。たとえ小さくてもいいので、「本当に応用できる先(尖ったニーズ)がある技術」であるかどうかを、強く意識するようにしています 。
─日々の業務の中で、最もやりがいや喜びを感じるのはどのような瞬間ですか?
荻野:まだ入社して1年半ほどですが、投資先の企業がどんなに小さなことでも「うまくいった瞬間」に立ち会えた時は嬉しいです 。
例えば、新しく受注が取れた、売上が上がった、資金調達がうまくいった、採用が成功した、といった報告を受けると、まず純粋に嬉しいです 。そして、その結果に対して、自分が少しでも貢献できていたと思えた時には、さらに大きな喜びを感じます 。
究極的には、自分が何かしら貢献できた会社が「上場」した時が、一番嬉しい瞬間なんだろうなと想像しながら、日々の業務に取り組んでいます 。
「変数」でありたい。当事者として事業成長に貢献する支援スタイル
─XTech Venturesは「起業家と共に事業を創造する」という思想を大切にされていますが、他のシード系VCと比較して、特に「XTech Venturesならでは」と感じる投資の面白さや支援のスタイルはどのような点にありますか?
荻野:支援のスタイルという点では、最近、会社のバリューを「自らも変数であれ」というものに変えました 。これは、我々キャピタリストが、投資先の事業における何かしらの「変数」となれるように貢献していこう、という決意の表れです。大前提として、VCはあくまで第三者であり、スタートアップに対して大きなことができるとは考えていません 。
ですが、その中でも「できることはすべてやろう」という思いで、このバリューを掲げています。例えば私自身も、次のラウンドの資金調達を目指す投資先の企業と深くディスカッションし、一緒に資金調達の資料や事業計画を作成し、投資家回りをお手伝いして、結果うまく調達できたケースがありました 。もちろん、私が関与しなくてもうまくいったかもしれませんが、「もしかしたら少しでもプラスになったかもしれない」という観点で、できる限りの支援をしていく 。そこがXTech Venturesのスタイルであり、面白さだと感じています 。
─XTech Venturesという組織の強みやユニークな点はどこにあるとお考えですか?
荻野:投資哲学のユニークさがあると思います。一般的にVCは「ホームラン案件」、つまりユニコーン(時価総額1000億円超)になる企業に投資するのがセオリーとされています。
しかし、XTech Venturesは、そこに対して強すぎるこだわりは持っていません。もちろん大きな成長を目指しますが、例えば、シードラウンドのバリュエーションが低く、将来的に100億円規模での上場が見込め、投資倍率として十分なリターンが期待できれば、そこにもしっかりと投資検討を行います。
「必ずしも超巨大なホームランにならないと投資しない」というわけではないのが、弊社の特徴です。このスタンスがあることで、例えば「すごくニーズはあるけれども、市場自体は少しニッチな業界」といったスタートアップにも投資ができます。
この投資スタイルの結果として、XTech VenturesはシードVCでありながら、エグジットの「打率」が比較的高く出ています 。ホームランだけを狙わなくても、しっかりとエグジットし、ファンドとしてリターンを出す。そういった投資を実現している点も強みです。

技術だけではなく、ニーズに惚れる。苦い経験から学んだ投資の「目」
─荻野さんがベンチャーキャピタリストとして最も大切にしているスタンスは何ですか?
荻野:まず、私自身のバックグラウンドを活かし、いわゆる大学発のベンチャーや、技術ドリブンな会社にフォーカスして投資をしていきたい、という思いがあります 。
その中で、投資の意思決定をする際に最も意識しているのは、やはり「本当にニーズがある技術なのか」という点です 。これは、コニカミノルタ時代に「技術は良くても、ビジネスとして本当にニーズがあるのか分からないまま進んでしまい、事業化がうまくいかない」という経験をしてきたからです 。
「色んなものに応用できる」という技術は、裏を返せば「何にも応用できない」リスクも持ってます。私は「小さくてもいいから、確実に応用できる先(=尖ったニーズ)がある技術・事業か」という点を、起業家と向き合う上で最も大切にしています。
─今後、どのようなバックグラウンドやマインドセットを持った方にチームに加わってほしいですか?
荻野:バックグラウンドで言うと、私自身がメーカーやコンサルティングファームの出身なので、そうしたご経験をお持ちの方に来ていただけると嬉しいです。
ただ、それ以上にマインドセットとして重要なのは、「学習熱心な方」であることだと感じています 。VCの仕事は、日々新しい技術やビジネスモデルに触れます。そうした新しいことに対して「すごく知りたい」「勉強したい」と思える好奇心旺盛な方にとっては、その学習意欲自体が仕事に直結するので、すごく面白いのではないかと思います。
VCの経験は問いません 。弊社は基本的に、ほぼ全員がVC未経験で入社しているので、そこは全く気にしていただく必要はありません 。
─採用候補者の方にとって、XTech Venturesで働くことで得られる最大の成長機会や経験は何だと思いますか?
荻野:これはあくまで私の考えですが、ベンチャーキャピタルは、「経験値を積む場」という側面もありますが、それ以上に「これまでの経験を活かして、結果を出すフィールド」という側面が強いと思っています。もちろん未経験で入ってこられた後にしっかりと教育していく体制も整えていますが、どちらかというと、これまで様々な業界でご経験を積んできた方が、「自分のパワーを試してみたい」「本気で結果を出したい」と考えた時に最適な環境だと思います。
─ベンチャーキャピタリストとして、またXTech Venturesのメンバーとして、今後成し遂げたいことや実現したい世界観について教えてください。
荻野:私自身は今、大学発ベンチャーや技術系の会社への投資に注力しています 。まずはこの領域でしっかりと結果を出し、そういったディープテック系のスタートアップエコシステムの発展に貢献していきたいです。
そして、XTech Venturesという組織としても、そうした技術系の会社への投資でしっかりと実績を出し、今後も長く、継続的にそういったチャレンジングな領域に投資を続けていけるような体制を整えていくことに貢献したいと考えています。
─最後に、XTech Venturesに興味を持っている候補者の方々へ、メッセージをお願いします!
荻野:XTech Venturesは、本当に多様なバックグラウンドを持ったメンバーが入社して活躍している会社です。この記事を読んで、少しでもご興味を持っていただけたら、ぜひ一度カジュアルにお話させていただきたいです。まずはホームページの問い合わせフォームやSNSの私のアカウント等なんでも良いので、お気軽にご連絡いただければと思います。
◼️募集要項:こちら
◼️カジュアル面談: 荻野