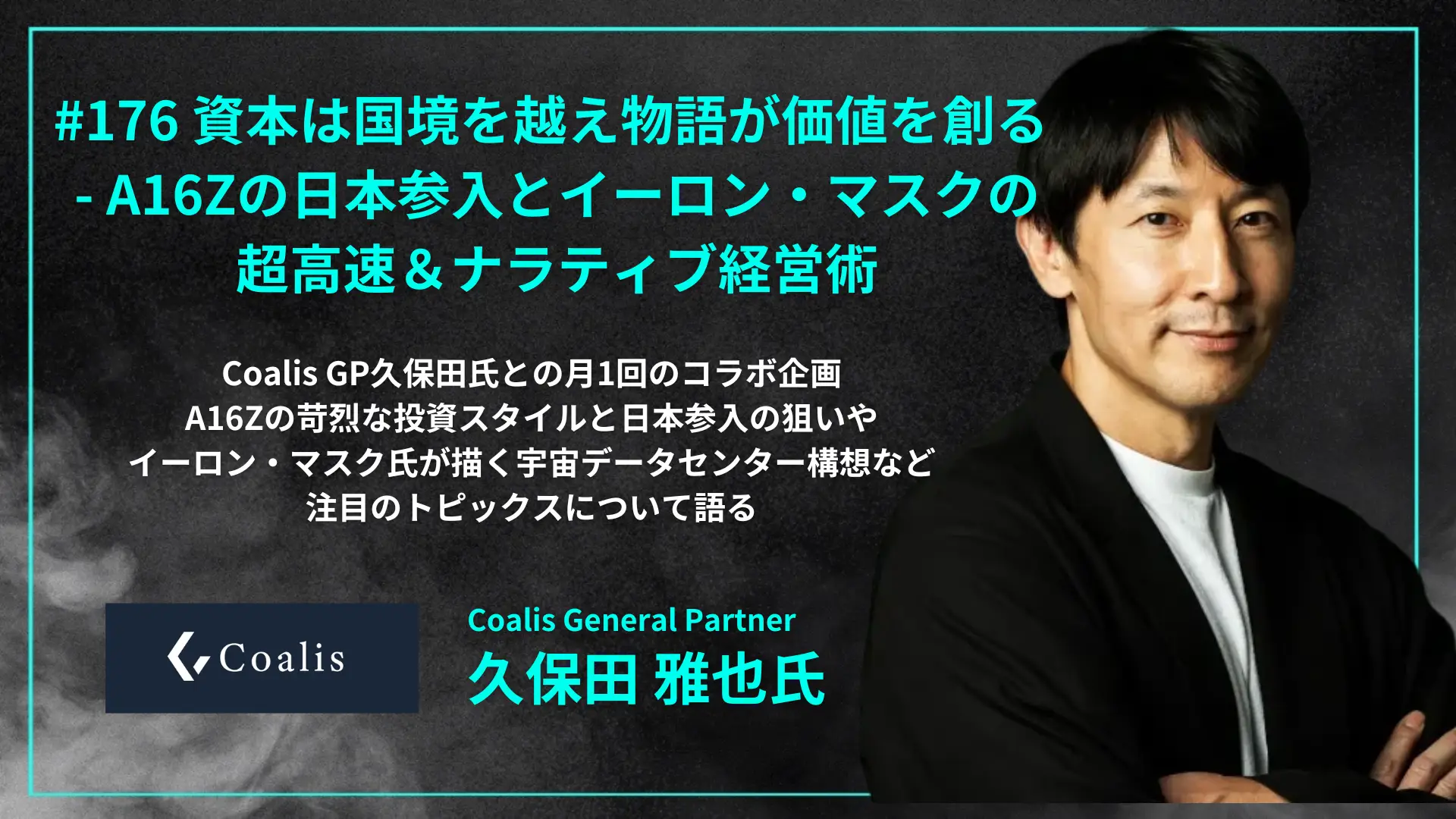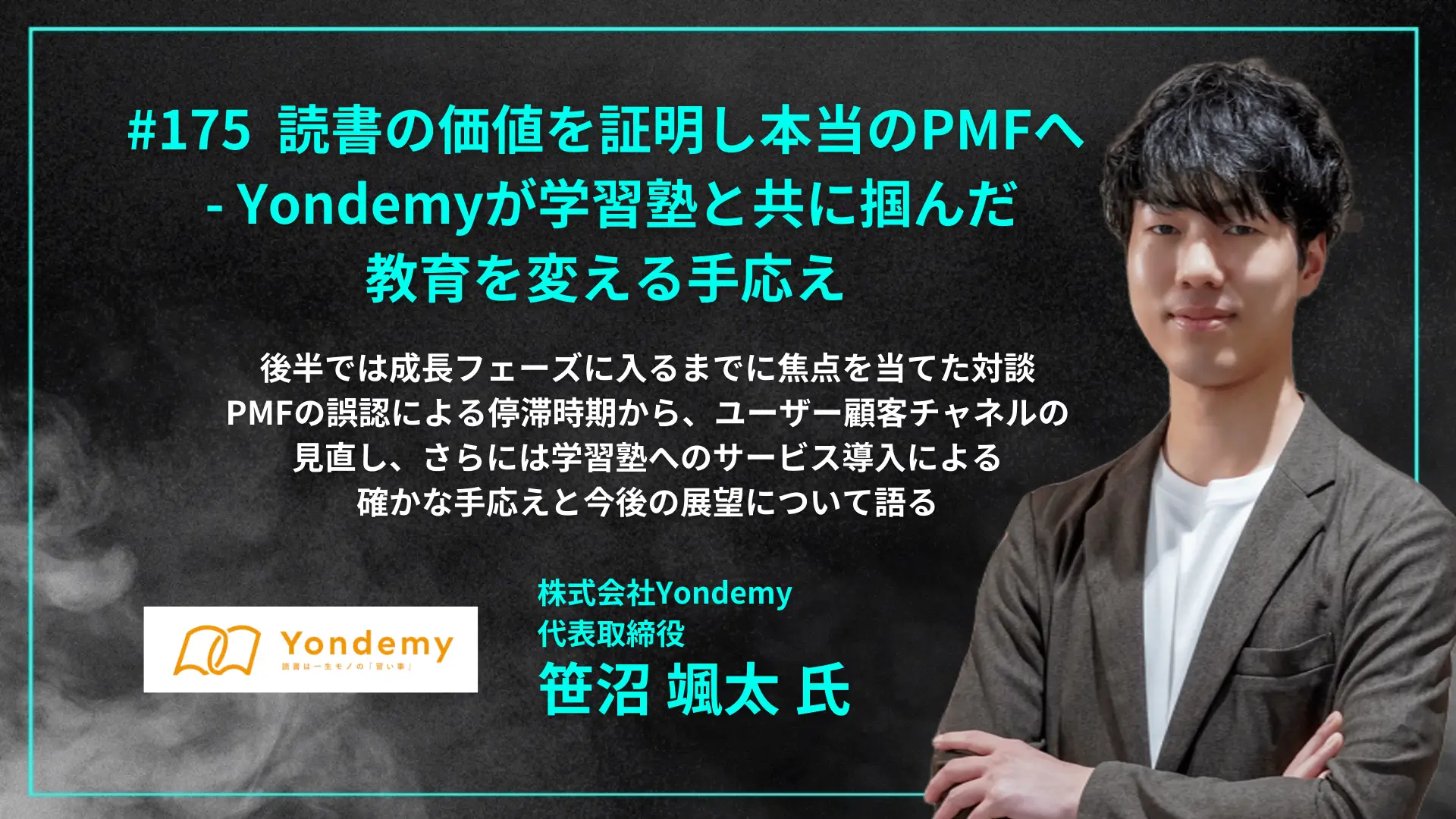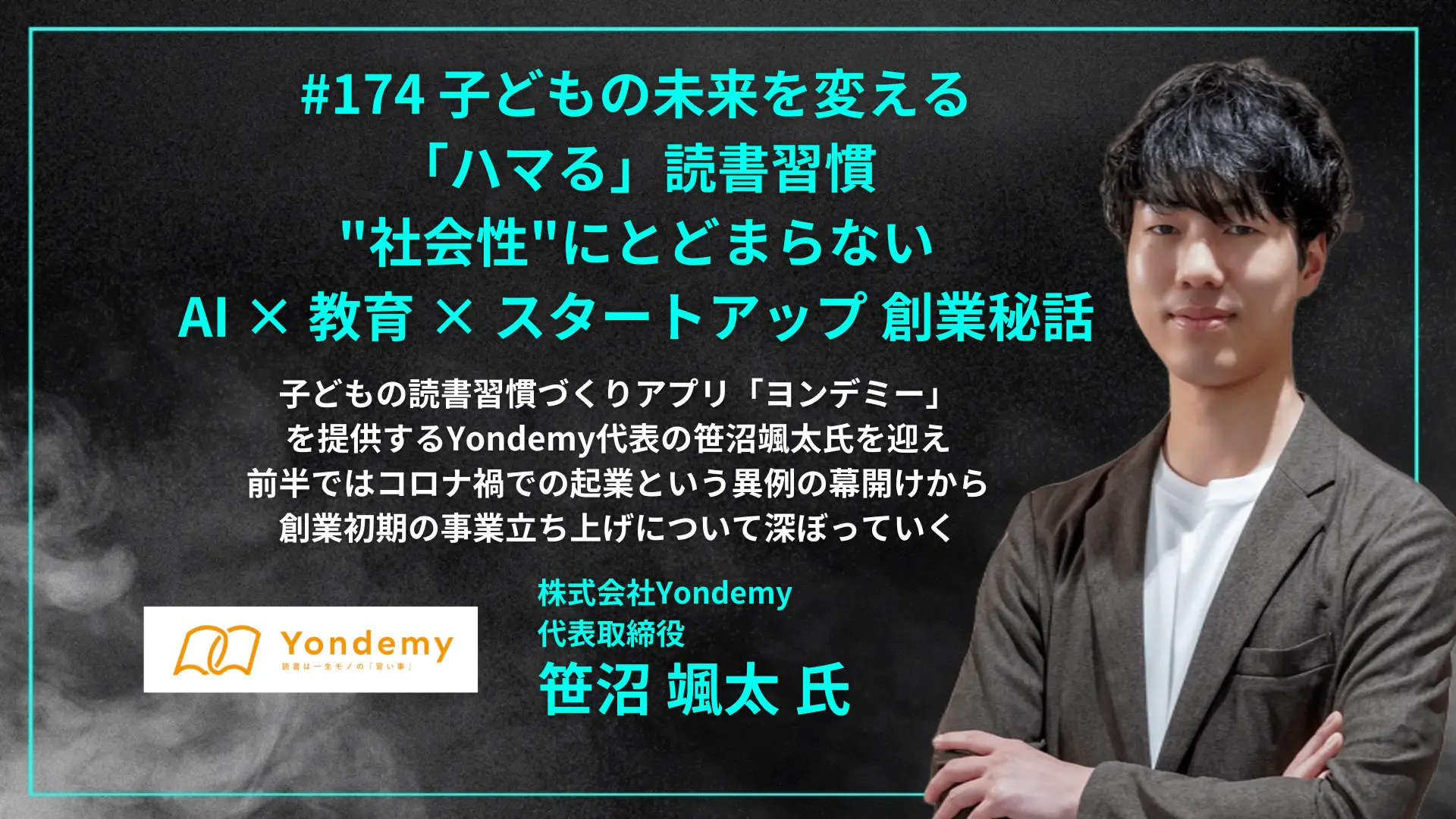投資先の「変数」であれ。XTech Venturesが描く、次世代キャピタリストの理想像(手嶋 浩己)

2018年の創業以来、シード・アーリーステージのスタートアップを中心に支援を続けるXTech Ventures。国の後押しもあり、シードVCが急増し、競争が激化する現在の市場環境。
その中でXTech Venturesは、どのような哲学を持ち、どのような未来を描いているのでしょうか。今回は手嶋に、創業からこれまで、現状の立ち位置、今後の展望、そしてVCとしての独自の強みやキャピタリストとして参画する醍醐味について、詳しくお話を聞きました。
博報堂に新卒入社後、2006年インタースパイア(現ユナイテッド)入社、取締役に就任。その後、2度の経営統合を行い、2012年ユナイテッド取締役に就任、新規事業立ち上げや創業期メルカリへの投資実行等を担当。2018年同社退任した後、Gunosy社外取締役を経て、LayerX取締役に就任(現任)。平行してXTech Venturesを創業し、代表パートナーに就任(現任)。
手応えは「及第点」。代表が振り返る"率直な現在地"
─2018年の設立から7年が経ちました。これまでを振り返って、手応えはいかがですか?
手嶋:2018年にXTech Venturesを立ち上げましたが、VCを立ち上げるタイミングとしては悪くなかったのではないかな、と感じています。
投資先やファンド出資者に恵まれ、継続的にファンド組成できるようになり、また、リターンの面では一定の結果を出しつつあります。ひとまず「及第点」というのが率直な手応えです。もちろん、私たち自身の力不足もあり、まだ数千億円企業になるなど、突き抜けて大きな成果を出した投資先がすでに出てきているわけではありません。そこは今後の課題ですが、すでに投資している会社も含めて、これからのポテンシャルに期待しているところです。
想定外だったことを挙げるとすれば、もう少し組織化が早く進んでも良かったかな、という点です。一方で、事業を伸ばしていくために、個々のキャピタリストが投資先の「変数」となり、深くコミットしていくという基本思想は、創業時から一貫して実践できています。
─この7年でシード・アーリーステージのスタートアップに投資するVCの数も急激に増えました。日本のスタートアップ市場や投資環境も大きく変化してきたと思いますが、その中で、現状のXTech Venturesはどのような立ち位置にあるとお考えですか?
手嶋:この数年で、シード・アーリーステージに投資するVCは非常に増えました。これは政府がスタートアップを後押ししていることが大きな要因です。政府の資金が入ったり、新たにファンドビジネスを始める際の後押しをしたりと、特に若い世代にとっては一定規模以上で新しくVCを立ち上げやすい環境が整ってきています。
その結果、「若い起業家を見つけて2,000〜3,000万円を出資して応援する」というスタイルのVCが急増し、その領域は競争過多になっている側面もあります。そういったVCと競争するのではなく、私たちは彼らとは違う戦い方をしなければなりません。
ベンチャーキャピタリストという仕事は、究極的には「個人技」であり、投資家と起業家が1対1で向き合い、「この人と一緒にやりたい」と思ってもらえるかに尽きます。私たちは、そうした関係性を築く中で、他とは少し違う雰囲気や価値を提供できる存在でありたい、と考えています。単なる資金提供者ではなく、事業の成長に深くコミットする姿勢を打ち出すことで、独自の立ち位置を確立できているのではないかと思います。
─XTech Venturesとして今後、注力していきたい投資領域やテーマがあれば教えてください。その背景にある考えや市場分析についても聞かせてほしいです。
手嶋:私たちは、ファンドとして「この領域に注力する」ということを、あえて決めすぎないようにしています。先に特定の領域を掲げてしまうと、それ以外の大きなチャンスを逃してしまう「機会損失」につながりかねないからです。
もちろん、キャピタリストとして様々な分野について浅く広く知っておく努力は欠かせません。しかし、最終的にはその領域で事業を立ち上げようとしている起業家の方が、私たちよりも圧倒的に詳しい。だからこそ、我々は先入観を持たず、まっさらな状態で話を聞くことを大切にしています。「これは注目領域だ」「このビジネスはあり得ない」といったバイアスをかけず、話を聞いて「なるほど、そういうことだったのか」と理解し、判断する。もし知識が足りなければ、2〜3週間かけて集中的に勉強すればいいのです。
世間的に「成長領域」とされているテーマが、ゼロからスタートアップを立ち上げて成功できる領域と一致するとは限りません。例えば「フィジカルAI」が注目されているからといって、すでにソフトバンクグループなど同じ領域で巨額の買収を行うような大企業が存在する市場で、どのような立ち上げ方がスタートアップにとって勝ち筋があるのか。私たちは、そうした流行りの言葉に惑わされず、ゼロから事業を立ち上げることの難しさと向き合った上で、投資判断を行うようにしています。

「個の力」から「組織力」へ。これから見据える"チームで勝つ"未来
─少し視点を変えて、組織としてのXTech Venturesについても教えてください。今、どのようなフェーズにあるのでしょうか?
手嶋:1号、2号ファンドでは、私や共同代表の西條が先頭に立って走ってきましたが、3号ファンド以降は、よりチームとして、組織力で継続的に成果を出していくフェーズに明確に移行していくつもりです。将来、パートナーとしてファンドを牽引していける人材を、これから4〜5年かけて育てていかなければならない、と考えています。
創業当初は、私や西條と若手メンバーの間で、経験や視座に大きな差があり、コミュニケーションの難しさもあったと思います。しかし、その過渡期を乗り越え、今では経験を積んだメンバーが中核を担ってくれている。新しく入る方にとっては、経営陣の意図を咀嚼して伝えてくれる先輩がいるため、ストレスなく業務に集中できる環境になったと感じています。
─XTech Venturesの組織が拡大する中で、新たに見えてきた「壁」や「課題」などは何かありますか?
手嶋:創業から7年が経ち、振り返ってみると、もう少し組織化が早く進んでも良かったかもしれない、という点は課題として感じています。個々のメンバーの力に依存する部分が大きかったフェーズから、チームとしてより大きな成果を出せる体制へと移行していくことが、現在の課題でもあり、そこに挑戦しているところです。
─そうした課題を乗り越えていくために、今後XTech Venturesに入社される方にはどのような役割を期待しますか?
手嶋:「とにかくネットワーカーになって沢山の起業家をファンドに連れてきてほしい」といった、ソーシングだけの役割を求めることはありません。私たちは、将来のパートナーを育てることを目指しています。
投資という仕事は、ベンチャーキャピタリストの仕事全体の3割くらいに過ぎません。残りは、投資した会社にどう少しでも貢献していくか、そしてファンドレイズ含めて出資者とどう向き合うか、組織的活動をどう回していくか、といった業務です。
新しく入る方には、最初からそうしたファンド運営の全体像に関わってもらいたいと考えています。投資した以上は最後まで伴走し、どんな局面であっても会社にとっての「変数」になろうと努力する。そのような、本質的なベンチャーキャピタリストを目指す気概のある方を求めています。

ポジショントークはしない。媚びない姿勢が、"本質的な信頼関係"を生む
─シードVC間の競争も激しくなっています。その中で、XTech Venturesが今後さらに選ばれ続ける存在になるために、どのような点を強化していく必要があると考えてますか?
手嶋:最低限の認知を獲得するためのPR活動は必要ですが、最終的に起業家が投資家を選ぶのは、1対1で向き合った時の相性や信頼関係です。小手先のブランディングで選ばれるとは考えていません。
その中で私が意識しているのは、「案件を取るためだけのポジショントークをしない、過度な営業をしない」ということです。多くの投資家は、案件を獲得するために「全力で応援します」「我々にはこんな支援ができます」と、耳障りの良い言葉を並べるかもしれません。しかし私は、逆に「投資を受けるかどうか、最終的にあなたが決めることだ」というスタンスを貫いています。
一見、冷たく聞こえるかもしれませんが、媚びずに本質的な議論をすることで、かえって信頼関係が生まれ、「ぜひ手嶋さんにお願いします」と言っていただけるケースが年に数回は起きます。起業家向けの営業トークが通用しにくくなっている今、正直でフラットなコミュニケーションこそが、我々の強みになると考えています。もちろん、とはいえ当社もまだ実績不足なメンバーはとにかく熱意を伝えて振り向いてもらう努力は必要と思いますし、単純に私のスタイルを真似しては結果は出ませんよね。
─組織としての進化を遂げた上で5年後、10年後にXTech Venturesはどのようなベンチャーキャピタルになっていたいですか?
手嶋:「実力派のベンチャーキャピタリストが少数精鋭で集まっているファンド」として認知される存在になりたいですね。ここで言う「実力派」とは、ソーシングから投資実行、そしてIPOやM&AといったEXITまで、企業のあらゆる成長フェーズにおいて、一貫して何らかの価値を提供し続けられるキャピタリストのことです。
VCの中には、とにかく多くの起業家と会い、数を打って投資し、有望そうな投資先を次のラウンドのVCに繋いだら、あとはお任せする、というスタイルもあります。
しかし、私たちはそうありたいとは思いません。投資先の事業や会社の成長に深く関与し、キャピタリスト自身が「自分がいたからこそ、この会社はここまで成長できた」という爪痕を残す努力を最大限する。起業家から見れば、VCがやれることは限られるかもしれませんが、少なくとも、そのつもりで貢献意識を強く持つ。そうでなければ、人知れず株を売買する上場株投資と変わりません。
投資先の成長の「変数」になれるようなキャピタリストを育て、輩出していくこと。それが、XTech Venturesがエコシステムにおいて、なくてはならない存在になるために最も重要だと考えています。
目指すは「実力派の少数精鋭集団」。"リレー方式"を選ばないVCの未来図
─手嶋さんが、起業家と向き合う上で、最も大切にしている「スタンス」は何ですか?
手嶋:先ほども触れましたが、「無理に案件を取りにいこうとしない」という姿勢です。案件獲得を目的化すると、どうしてもコミュニケーションがポジショントークに偏ってしまいます。自分の思考にもバイアスが生まれます。そうではなく、あくまで何か役に立てるパートナーとして、「あなたの事業にとって、我々と組むことが本当に最善なのか」という視点で、率直に議論することを心がけています。
そのために、先入観を持たずに、常にニュートラルな状態で情報に接する。世の中のトレンドやバズワードに流されず、一つひとつの案件に対して「なぜ今、この事業なのか」「本当に勝ち筋はあるのか」をゼロベースで考える。
起業家の話を真摯に聞き、必要であれば短期間で徹底的に関連分野を勉強する。この地道なインプットの繰り返しが、判断軸を研ぎ澄ます上で不可欠だと考えています。
─若手のキャピタリストがXTech Venturesで成長するために、最も重要だと考えるスキルやマインドセットは何だと思いますか?
手嶋:短期的にうまいことやろうとしない、ということです。多くのVCは、シードで投資したら、シリーズAのリード投資家を見つけてバトンタッチする「リレー方式」を取ります。金融業としては、その方が効率的だからです。
しかし、私たちは非効率であっても、出来うる限り投資した会社には貢献し続けたい、うまくいかない時も一緒にもがきたいと思っています。なぜうまくいかないのかを共に悩み続ける。その経験こそが、人を成長させ、この仕事のやりがいに繋がると信じています。金融業としての効率性よりも、投資家としての本質的な成長を求めるマインドセットが重要です。

求めるのは「素直な学習意欲」。ワークライフミックス"を楽しめるか?
─どのようなバックグラウンドやスキルセットを持つ方と一緒に働きたいですか?
手嶋:金融や経営に関する知識が最初から豊富にある必要もないと思っています。それよりも、入社前に「これを読んでみてください」とお願いした際に、それを面倒くさがらずに実行できるような、素直な学習意欲があることの方が重要です。
第一に「好奇心」が旺盛な方。知らないことや新しいことにワクワクできる人は、この仕事に向いています。次に、「先入観を持たずに行動できる」方ですかね。
そして、物事を「めんどくさい」と思わないことも大切です。また、過度にワークライフバランスを重視する方は、少しミスマッチかもしれません。
もちろん、深夜や休日の労働を推奨するわけでは全くありませんが、仕事とプライベートを完全に切り分けるのではなく、ある種ミックスした感覚で楽しめる人の方が、ストレスなく働けると思います。
─XTech Venturesで働くことで、どのような成長機会やキャリアパスが得られるでしょうか?
手嶋:大きく2つの成長機会があります。1つは、先ほどからお話ししている通り、投資先のステージによらず、創業からEXITまで一貫して支援に関与できることです。会社のあらゆる局面を起業家と共に経験することは、何物にも代えがたい成長の糧となるはずです。
もう1つは、キャリアの初期段階から「ファンドマネージャー」としての視点を持って働けることです。多くのVCでは、若手はソーシングやデューデリジェンスの一部といった特定業務しか担当させてもらえないことも少なくありません。
私たちは、ファンドレイズやLP投資家とのコミュニケーションも含め、ファンド運営の全体像に触れる機会を積極的に提供します。これは、将来独立して自分のファンドを持ちたいと考えている方にとっても、非常に魅力的な環境だと思います。
─最後に、この記事を読んでいる未来の仲間候補へ、メッセージをお願いします!
手嶋:VCという仕事に興味はあっても、何をやっているのかよく分からず、応募をためらっている方は多いと思います。決して怖い場所ではありませんので、少しでも興味があれば、一度アクセスしてみてください。
もちろん、お話をする中で、率直に「この仕事には向いていないかもしれません」とお伝えすることもあると思います。しかし、それはお互いにとって必要なこと。私たちは、熱意だけで来ていただくことを歓迎しますが、その後のプロセスでは、自ら学ぶ姿勢を求めます。この記事を読んで、少しでも心が動いたなら、ぜひ一度お話を聞きに来てください。未来の日本のスタートアップシーンを共に創っていく仲間と出会えるのを、楽しみにしています!
◼️募集要項:こちら
◼️カジュアル面談:手嶋