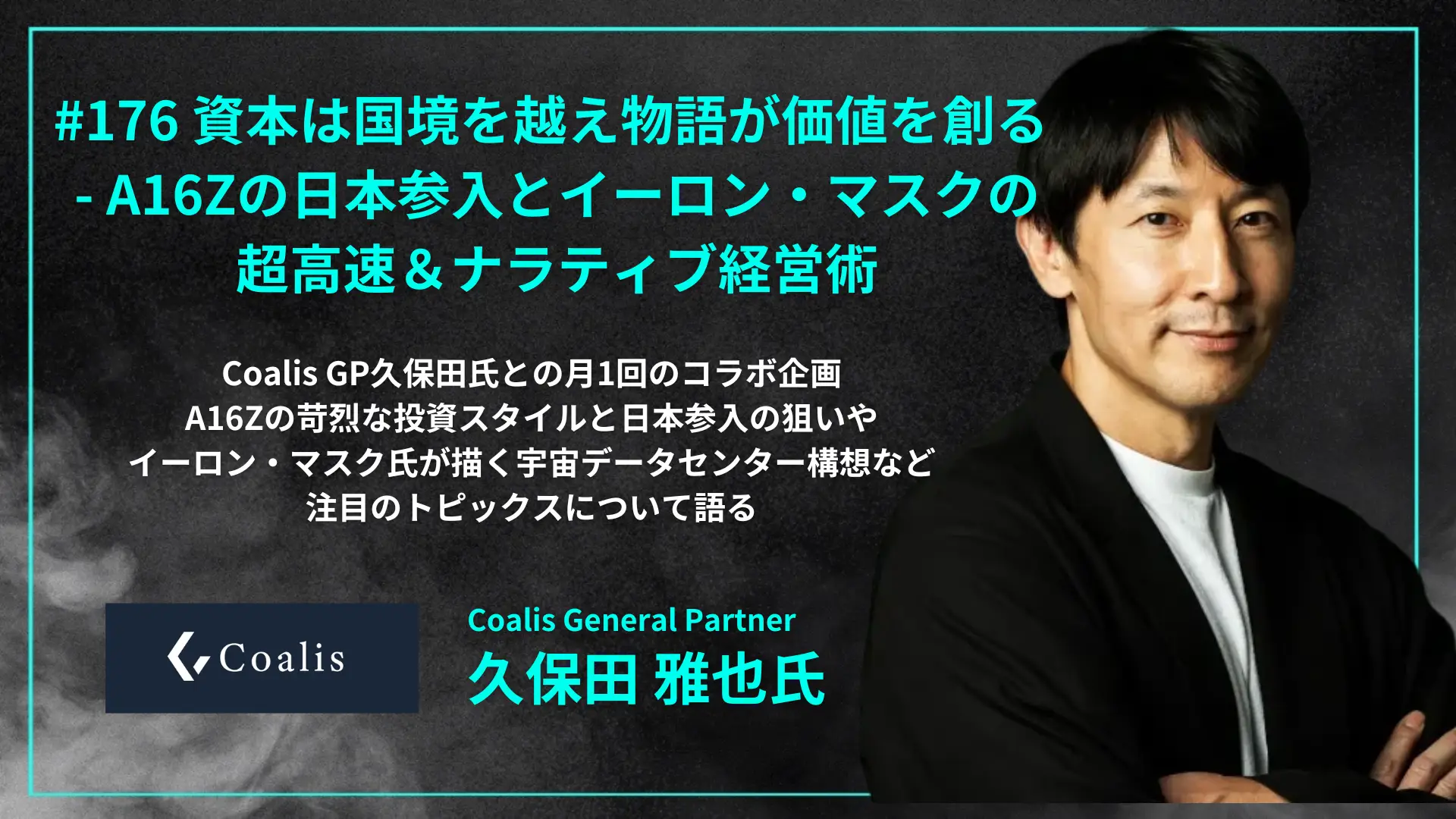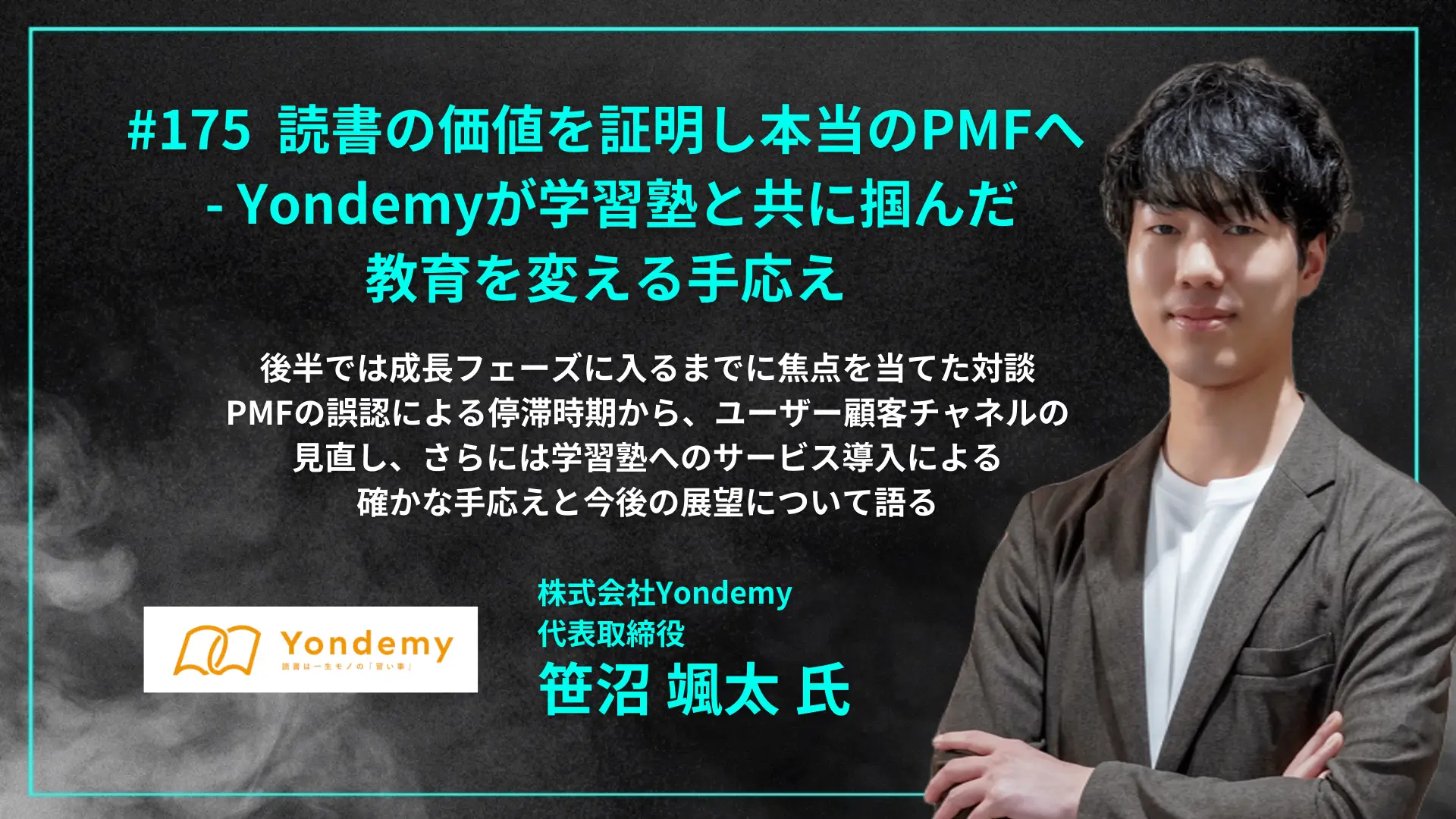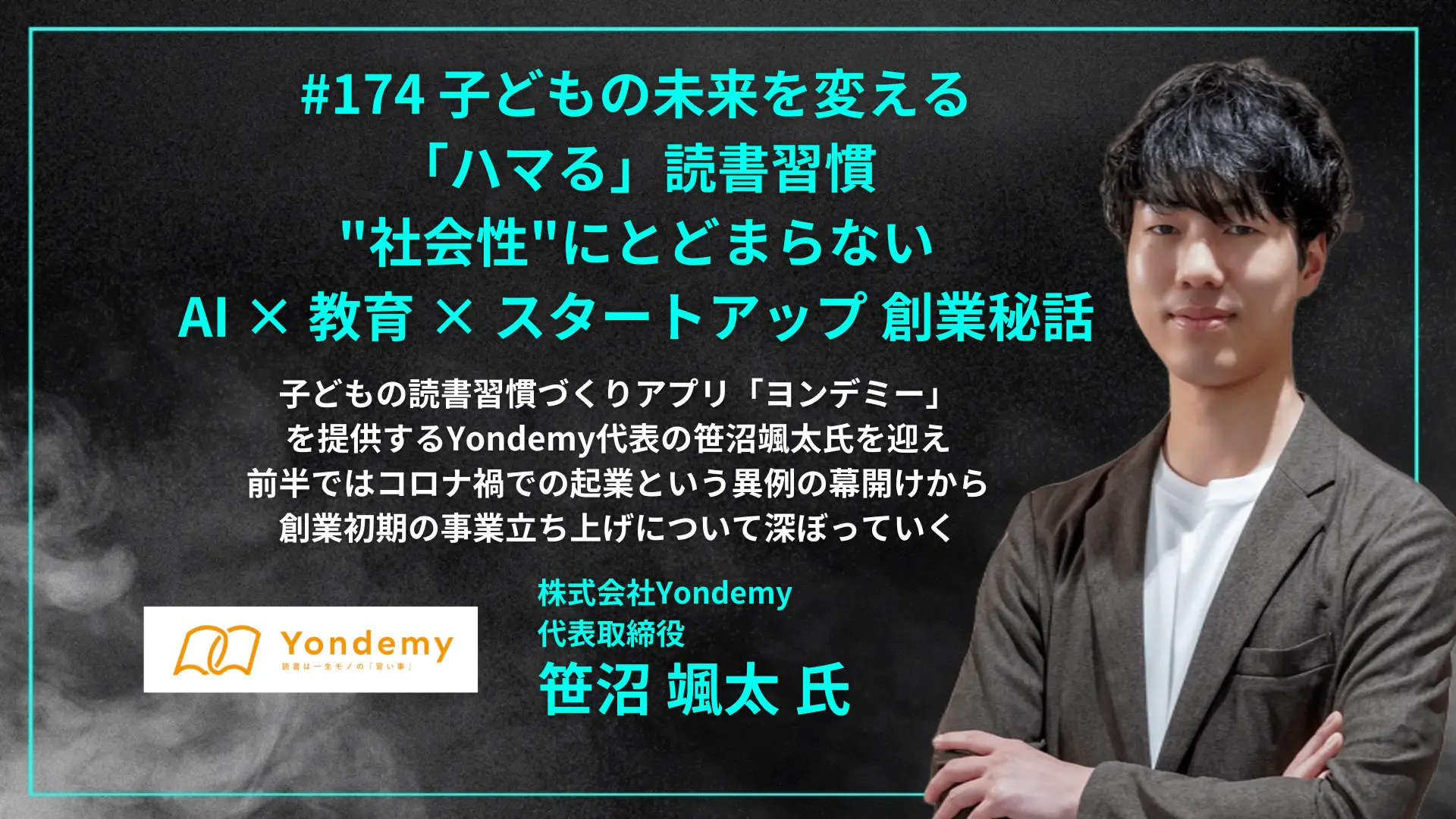#8 フィンテック歴20年の起業家がチャレンジャーバンクに挑戦する理由 「ナッジ」を立ち上げた思いに迫る ー ナッジ沖田貴史氏
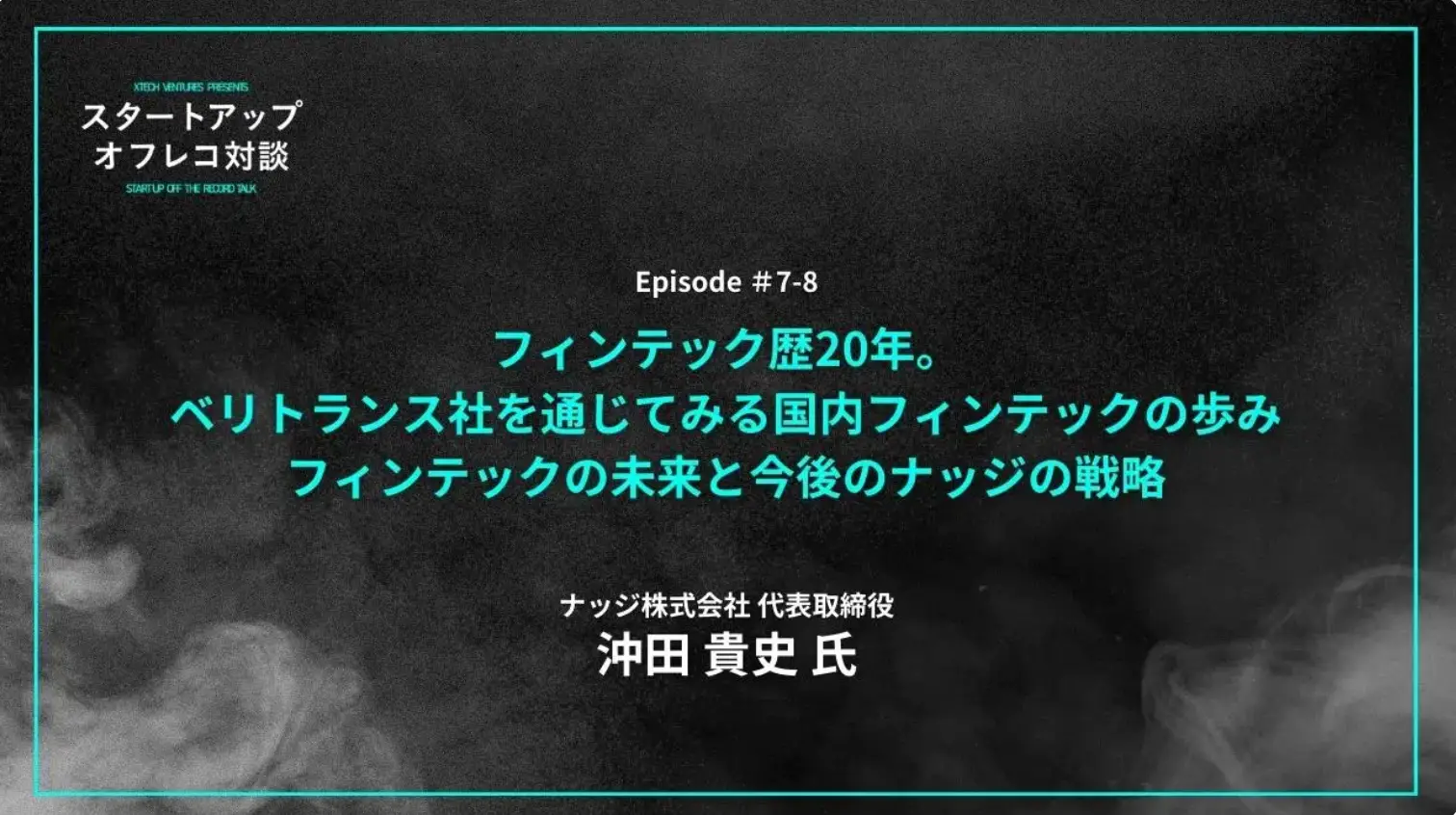
「スタートアップ オフレコ対談」は、XTech Venturesの代表手嶋とゲストの方をお呼びして対談する番組です。今回はフィンテック歴20年、ナッジ株式会社代表の沖田氏をゲストに迎えます。後半は、そんな沖田氏が設立した「ナッジ」の挑戦について伺います。次世代型クレジットカード決済サービスを提供する同社は、すでに累計調達額が10億円以上(2024年末時点では約46億円)。フィンテックという枠組みの中で、なぜクレジットカード事業からスタートしたのか。そして沖田氏が考えるフィンテックの未来について伺いました。
スピーカー
・沖田 貴史 氏(@OKITATakashi)
ナッジ代表取締役
・手嶋 浩己(@tessy11)
XTech Ventures代表パートナー
目次
# ナッジの事業内容、コンシューマービジネス領域の選択理由
# ナッジの展望と、沖田氏が考えるフィンテックの未来
※記事の内容は2021年11月時点のものです。
ナッジの事業内容、コンシューマービジネス領域の選択理由
手嶋:ここからは、ナッジで今チャレンジしてる内容を聞いていきたいと思います。金融領域でいくと、最近はBtoBのフィンテックスタートアップもかなり増えてますし、いろんな切り口でいろんな会社が入り乱れてますが、沖田さんもベリトランス含めてBtoBの世界でずっとやってきた方だと思ってます。
数年前に事業ドメイン決めたと思うんですけど、フィンテックの中でもなぜこのコンシューマービジネスの領域を選んだのか。今何をしているのかも含めて教えてもらえますか?
沖田:今回はBtoCですが、BtoBのエッセンスも含んでいます。まず大きい枠組みで言うと、チャレンジャーバンクをやろうというところですね。
手嶋:チャレンジャーバンクって何ですか?
沖田:これはよく聞かれるんですが、文字通り「挑戦する銀行」ですね。既存の銀行に対しては、人によっていろんなイメージがあると思うんですけど。手嶋さんの銀行のイメージってどんな感じですか?
手嶋:街角にある物理的な店舗っていう感じがありますね。
沖田:店舗だと待たされるとか、15時になるとシャッターが閉まるとか、あんまりポジティブでないイメージが正直多いと思います。銀行もサービス業の一つなので、サービスを良くしていきましょうよというところで、今インターネットとかテクノロジーの会社ってUXめちゃくちゃ良くなっているじゃないですか。なので、今時の常識的な考えで銀行をプレイヤーとして再度デザインし直そうというのがチャレンジャーバンクですね。
手嶋:なるほど。どうして日本で、このタイミングでチャレンジャーバンクをやろうと思ったんですか?
沖田:前職のときに、銀行さんと一緒にやっていて、中に勤めている人たちってやっぱりみんな優秀なんですよ。一人ひとりはすごく誠実で良い人なんですが、会社という組織になると、伝統が重要みたいなイメージがどうしてもある。人々が持つ銀行に対するイメージとか、銀行が銀行に対して持つイメージゆえに、新たなことにチャレンジしづらいんですよね。
これってビジネスオポチュニティとしては大きいんですよ。金融ってなくてはならないものだけど、なかなか変革が起きていない。であれば、もうこれはむしろチャンスじゃないかと思って飛び込みました。
手嶋:僕はある程度使わせてもらって知ってるんですけど、ナッジはまずどういったサービスから参入してるんでしたっけ?
沖田:1回戦目は、クレジットカード。
手嶋:どういうクレジットカードなんですか?
沖田:スマホと連動する形で、安心・安全・使いやすいっていうのが特徴ですね。あとは、そのカードを使うだけで、自分の好きなスポーツ選手やアーティストを応援できるんです。
手嶋:応援できるってのは、どのように応援できるんですか?
沖田:利用額の一部がそのアスリートやアーティストに回っていきます。今後はNPOなども対象に寄付もやっていく予定です。
手嶋:なるほど。ちなみに私は格闘家の堀口恭司さんのカードを発行しています。使えば使うほど堀口さんの応援になるのかなと思って、使わせていただいてますね。リリースしたのはいつでしたっけ?
沖田:リリースは2021年9月ですね。
手嶋:Visaのプラットフォームを使って参入してる感じですかね。
沖田:そうですね。
手嶋:クレカ事業への参入って、素朴な話、やるぞって決めてからどれぐらい時間かかったんですか?
沖田:会社を正式に作る前に、最初はジョイントベンチャーを立ち上げてるんで、通算すると2年ですね。
手嶋:なるほど。やっぱりそれぐらいはかかるものですか。
沖田:そうですね。スタートアップではVisaプリペイドが多いと思うんですけど、それだったらそんなにかからないですね。1年あれば十分だと思います。
手嶋:クレカの事業って、ある意味、与信を提供していくわけじゃないですか。素朴な疑問の2つ目としては、自社の資金って大量に必要なんでしょうか?
沖田:結論としては必要ですね。
手嶋:そこはやっぱり、沖田さんのバックグラウンドがあるから参入できる状態を作れたっていう感じですか。クレカ事業って若者が急に参入できないですよね。参入障壁がかなり高いというか。
沖田:そうですね。Visaプリペイドでも高めなんですけど、クレジットになるとさらに高いですね。
手嶋:サービスインして、まだ出だしだと思うんですけど、最初の想定と比べてどんな感じでしょうか。
沖田:結論からすると、最初に思っていた方向性としては極めて正しいです。想定していたよりもさらに良かった。仮説を上回ったので、ちょっと驚きの初速という感じですかね。
手嶋:というのは、ユーザー獲得もそうですし、獲得したユーザーのカードの使い方も含めて、全体的に想像以上にすごいなって感じですか?
沖田:そうですね。結局プリペイドよりもクレジットを選んだのは、その人の生活のあらゆるキャッシュレス決済に入り込みたかったんですよ。プリペイドだと、特定用途がやっぱ多いんですよね。ですけど、その人のメインカードになって、月20万ぐらいは使ってもらいたいと思っていて。もちろん若い人向けなんですけど、若い人のほうがより可処分所得があるので。最初は我々の株主であるセゾンさんよりも顧客単価を高く設定していたんですよ。サービスを始めて2ヶ月で、彼らの倍以上になりましたね。
手嶋:ユーザーあたりの利用金額が。なるほど。
沖田:なので、獲得コストが安いというのも一つあるんですけど、それ以上にアクティブの度合いが高い。
手嶋:僕の「堀口恭司を応援したい」みたいな、他のクレカをすでに持っているけど誰かを応援したいから使う人もいると思うんですけど、ナッジのクレカだけ使ってるという人もいるんですか?
沖田:おそらくいますね。今回ちょっと規制緩和で、従来とは違う与信モデルを導入してよいということになっているので。
手嶋:おっ、その辺聞きたいですね。なんですかそれは?
沖田:たとえば、手嶋さんは大丈夫だと思うんですけど、フリーランスの方とか僕とか、起業した直後ってクレジットカードを作りにくいんですよ。それから、今時の働き方ですが副業・兼業をしている人も、一定の収益があったとしても作りにくい。
それは別にカード会社が意地悪しているわけではなくて、「多重債務にならないように」という規制上の配慮があって。そこがサラリーマンを前提にして構築されているので、時代の変化に追いついてなかったんですよね。
ナッジではそれを全面的に見直しました。10万円以下という制限はあるものの、その金額内であればもう少し与信の自由度を上げていきましょうという法律の改正が去年行われて、実際には2021年の4月からその制度がスタートしてます。
手嶋:そうすると、カードの会員になる際の審査の方法が根本的に違うんですね。
沖田:そうですね。審査方法も違いますし、審査項目が違うんですよ。カードを作るときって、入力事項がいっぱいあるじゃないですか。名前とか住所とか、勤務先、年収、持ち家なのかとか、家族構成とか。100項目くらい書く必要があると思うんですけど、ナッジだと自分で入力するのは三つだけなんですよ。
手嶋:何と何と何ですか?
沖田:電話番号と氏名。あともう1か所だけ(暗証番号)。あとは基本的に本人確認書類をOCRで読み取るので、入力そのものが不要になってますね。
手嶋:とはいえいろいろと不正も起きる業界だと思うのですが、どういう情報を重視しながら審査するんですか?
沖田:たとえばアプリの使い方。立ち上げる頻度や入力スピードとかを重視するんですけど、そういったデータがどんどん蓄積されていくので。それに今は正式なライセンス事業者なので、信用情報にアクセスできるんです。要はブラックリストですね。
ブラックリストに載っている方は、ナッジに申し込んでいただいても残念ながら審査で落ちてしまうんですが、初めてカードを持つ方や、過去の使用歴できちんと返済が確認できている方は、フリーランスになったり転職したりしても、その人のこれまでの行動を重視して信用情報としています。
手嶋:ナッジは新しい会社でゼロから新しい考え方を確立できたと思うんですけど、「既存のクレジット会社もそうすればいいじゃん」と思う人も多いかもしれない。やっぱりできないものなんですか。要するに、弾いてしまっている人たちが存在するわけですよね、お金になるのに。何か理由があるんですか?
沖田:できない理由もありますし、やる必要もないっていう面もありますね。カード業界って生まれて50年ぐらいなんですけど、これまでほぼずっと右肩上がりなんですよ、増収増益です。グレー金利で一瞬ダメージを食らったときはあるんですけど、それを除くと40年以上、増収増益できている。クレジットカードの利用割合は3割ぐらいなんですけど、それだけでも十分でかいマーケットだというのが一つですね。
できない理由としては、技術負債が大きいんですよね。たとえば株主であるクレディセゾンの基幹システムって2000億円かかっているんですよ。2000億円って、メガバンクのシステムとそこまで変わらない。簡単そうに見えて実はすごく複雑なシステムになっているので、少しでも変更すると数億から数十億くらいコストが変わってしまうんです。
手嶋:なるほど。業界特有のイノベーションのジレンマがある中で、新たな需要が確実に生まれてるところをすくいにいっているんですね。ちなみに、そこを狙っていくと、貸倒率とかは通常のクレカ会社より高くなりそうな気がするんですけど、その点はどうですか?
沖田:まだ今の段階だと早すぎて、定量的には言えないですね。ただ、他のサービスって信用情報を見ないでやってるんですよね。ほとんどのフィンテックの小口貸出みたいなやつって。それでもだいたい数パーセント、似たようなモデルのところだと貸倒は1%あるかないかという感じ。なので少ないです。
あと我々はアプリを提供しているので、返済を促すPUSH通知を出せます。メッセージを出すとリアクションがはっきりわかるので、そういった意味では貸倒リスクについてはコントロールしていけるかなと思いますね。
手嶋:なるほど。今は上限額が10万円じゃないですか。そこはビジネスとしてその額に設定してるって感じでいいんでしたっけ。
沖田:今は法的なレギュレーションが要因ですね。
手嶋:法的なレギュレーションがあるんですね。一旦その範囲の中で、会員を増やしていくっていうのが今の注力ポイントですか?
沖田:そうですね。この中で会員を増やしていって、利用者のさまざなデータをもとに、もう少しダイナミックに与信をしていったり、サービスの機能を拡充させたりしていくつもりです。
ナッジの展望と、沖田氏が考えるフィンテックの未来
手嶋:そういう意味だと、まだ概念がはっきりと定義されないチャレンジャーバンクという大きくて抽象度の高い山にあらゆる入り口からみんながバーッとかけ上がっている状態。既存のプレイヤーも含めて今後参入してくると思うんですけど、ナッジは現在の入り口から、今後どういうステップで、どれぐらいの時間軸で何をやろうとしてるんですか?
沖田:チャレンジャーバンクってグローバルに見るとみんな似たような感じで、決済だけではなくて資産運用とか貸付をやったりとかみたいな相互連携に変わっていくんですけど。ナッジの場合は、そういったオーソドックスなやり方を取ってもいいと思ってますがし、ただ一方で1回戦目の決済事業だけでちゃんと黒字化する計画を立てているんですよ。当初は24ヶ月で黒字化の計画でしたが、このペースだと14ヶ月ぐらいで達成できそうです。
ユーザーにとって良いサービスはもちろん組み合わせて提供していきます。ただ「ユーザーは別に求めてないけど、収益化のためにはこれを抱き合わせで販売しなきゃ」みたいに、無理な多角化はしない。チャレンジャーバンクって自分たちで言ってますけど、その括りにとらわれる必要はないかなと思ってますね。
手嶋:状況を見ながら、臨機応変にやっていこうという感じですかね。沖田さんならではの戦い方でさすがだと思うのは、陣営の作り方が非常にオープンイノベーションだなと。先ほどから出ている株主のクレディセゾンも、競合じゃないのかと見る人もいると思います。あと凸版印刷や通常のベンチャーキャピタルも入っている。
自分の信用が使えるところは使っていくってこともあると思いますし、意図的にこういうところを巻き込んで、陣営を作っているみたいな、そこら辺の戦い方、仲間の作り方における工夫を教えてもらっていいですか。
沖田:ここは手嶋さんに教えてもらったところが結構多いんですよ。
手嶋:いやいや、僕は何もやってないですよ。
沖田:やっぱり、自分なりのやり方をとっていこうというところで。一言でいうとおっさん起業家じゃないですか。なので若い起業家が得意とすることに真正面で勝負するのではなく、過去の信頼・信用やトラックレコードを含めて、自分にできることをやっていこうっていうのが大きいですね。
あとは銀行の人たちに対してなんですけど、たとえばクレディセゾンもむちゃくちゃいい会社なんですよ。けどさっき言ったように、システムが大きいし、社員数も多いから、風通しが良い環境とはいえスローダウンしてしまう場面も多いんですよね。それに既存ユーザーがいるから、関係性をバッサリ切れなかったりするので。そういった意味では大企業に属する人たちが、スタートアップにいると「大企業にいる人は特に優秀じゃない」みたいな考えになりがちじゃないですか。
でも個を見るとそれぞれに良さがあるし、彼らだってスタートアップのような挑戦を本当はやりたいんですよね。だから「もうここは出島なんで、好きにやってくれ」と。向こう側のトップも望んでいるので、一緒にやりましょうよというふうに伝えています。セゾンで言えば社長の水野さんとかに了承を得て、来てもらっている人たちも伸び伸びとやってもらうのは意識しています。
手嶋:出向者を受け入れてやっているんですか?
沖田:はい、そうです。そういう人もいますし、出向じゃないけどほとんどナッジの人ですよねみたいな仕事の仕方をしている人も。
手嶋:ナッジの社内についてはベールに包まれているというか、あまりみんなに知られている状態ではないと思うんですけど。ナッジの組織って今どういう感じなんですか?
沖田:社員は10人ぐらいしかいないんです。
手嶋:そこはさっき言っていたように、長期戦にもなるし、臨機応変に動くために、まずは決済で黒字化しようという中で、意図的にリーンにやってる感じなんですか?
沖田:そうですね。やっぱり人が増えると、労務管理もしないといけないし、当然コストも上がるので。しっかり資金調達はしているし、ユーザーのことを考えつつも、あまり無駄遣いはしないっていうのが大前提ですね。
手嶋:素人目線ですけど、10人でクレカの事業ってできるんですね。クレカの事業って数十人いないと参入すらできないイメージがありますね。
沖田:それで言うと、社員は10人程度ですけど、フリーランスや副業兼業で入ってくれている人たちも入れると30人近いですね。
手嶋:外部の力も借りて組織を作れてるって感じですかね。
沖田:そうですね。あとさっきのオープンイノベーションやってる人たち含めると、サービス立ち上げ前のときにも120人とかいるので。大きい組織なんですけど、要は一人ひとりがプロフェッショナルとして働いてるみたいな感じ。メルカリさんに習って、いろんなものを勉強しています。
手嶋:いろいろなスタートアップがメルカリのケーススタディをうまく生かしてますよね。あとはフィンテック領域、コンシューマーのBtoBも、いろんなスタートアップが大勝負をかけていたり増えていったりすると思うんですけど。競争環境として、どういうプレーヤーがどのように産業をつくっていくのか。ここから先、何が起きるのか。どう見て経営をしていますか?
沖田:コンシューマー向けのビジネスって、独り勝ちするものが多いと思うんですけど。フィンテックは「Winner takes all」のものもあれば、勝者が分散して生まれるものも両方あるというのが真実だと思います。そういった意味では、いろんなプレーヤーがたくさん出てくるのは結論的にはすごくいいことです。それぞれが成功する可能性もあれば、どこか一つがドカーンと大きく成功する可能性もあると思ってますね。
手嶋:先日のPayPalによるペイディの買収はどう見ますか。
沖田:すごいいいことだと思いますよ。
手嶋:そこは沖田さんの中ではシナリオの一つでしたか?それとも、やっぱりちょっとびっくりしちゃったんですか?
沖田:全然びっくりしなかったとはもちろん言わないですけど。納得感はすごくあるので、なるほど、さすがだなっていうのが実感ですかね。
手嶋:「さすがだな」というのは、PayPalの人に対してですか。両方ですか。
沖田:両方ですね。
手嶋:なるほど、わかりました。そんな競争環境の中で、ナッジ自体は今シリーズAぐらいまでやったという感じですかね。
沖田:僕たちは「プレシリーズA」と言いましたけど、どういう表現が正しいのか。
手嶋:それも曖昧になってきてますよね。まあプレシリーズAって感じでしょうね、沖田さんがこれからやる勝負の大きさからすると。今後も調達をしながら大きい勝負をしていくと思うんですけど、1人でも「ナッジに入りたい」という人が出てくるといいなあと。ここから1年ぐらいで、どういう人材を求めてるかを最後に教えてもらえますか?
沖田:まず大きく二通りあると思っていて。一つは、高度人材ですね。今って、「普通に考えてスタートアップでそんなにレベルが高い人たちを採用しちゃって大丈夫なんですか?」と言われるような人にたくさん入社してもらっています。
たとえば、弁護士資格を持っているとか司法試験受かってますみたいな人が何人かいたり。テクノロジー的にも、我々が活用しているAWSのエンジニアで日本でもトップクラスの人もいます。僕たちは基本的には国内市場をターゲットにしているんですが、グローバルな教育を受けてきた人たちが圧倒的に多いですね。
その一方で、プロダクトマネージャーなど、現場でプロダクトを動かしてる人たちは20代がほとんどです。今のプロダクトマネージャーも25歳の女性なんですよ。
手嶋:フィンテックって、やっぱり挙動のエラーとかミスを起こしてはいけない感じがあるじゃないですか。カジュアルなプロダクト開発の経験者だときつそうな気がするんですけど、フィンテックプロダクトの開発は20代のメンバーでもやれるものなんですか?
沖田:トライアングル的な感じでやっています。管理系や経営層はかなりのプロフェッショナルで固めています。と言っても、30代がほとんどなのでシニアでもないんですけど。一方で、プロダクトの最前線は20代が本当に全部意思決定できるようにしてるんですよ。
手嶋:それはユーザー目線でっていうことなんですかね。
沖田:そうですね、マーケティングの面も含めて。ただ法律などのチェックはリアルタイムで必ずやってますので、「ここまではやっていい」という範囲を明確に決めて、その範囲内では権限委譲して自由にやってもらっている感じですね。開発チームも、センター的な開発チームメンバーとインフラ周りのメンバーが両方いるので、守りがしっかりしてる分だけバンバン攻められるという構造になってますね。
手嶋:なるほど。じゃあ、若くても何かしらのプロダクト開発の経験者とか、金融領域に興味があるエンジニアの人たちが、「興味本位で話を聞きたいです」というレベルでも大丈夫ですかね?
沖田:そうですね。プロフェッショナルな人材がたくさんいるので、刺激的で成長できる環境です。かつ、上が詰まってるってわけでもないので、本当に若くて、いい意味で野心的な人がフラットにカジュアルに働くには、すごく向いている会社だと思います。
手嶋:今は正社員が10人、業務委託などを含めて30人じゃないですか。2年後のナッジって何人ぐらいになってるんですか?
沖田:おそらくそれでも正社員は30人行かないと思います。
手嶋:そうなんですね。では5年後のナッジは?
沖田:5年後も、そんなに人は増やさないつもりです。
手嶋:少数精鋭で行くっていう感じなんですね。
沖田:そうです。なので「募集してます!」ってすごく言ってるんですけど、実はイスが結構埋まってしまってるんですよね。
手嶋:なるほど、狭き門だと。今、シリーズA前の検証期間中とはいえ、ユニットエコノミクスを見ながら、モデルを検証してる期間だと思いますけど。沖田さんはあまり誇張しないタイプなので、僕としてはかなりいいデータが取れてるのかなと感じたので。ぜひまたシリーズAに入ると会社の成長が感じられていいのかなと思いました。
日本の中で、もうフィンテックの生き字引的存在の沖田さん。前半はナッジを設立する前の、ある種、青春時代の話でしょうかね。北尾さんや伊藤穰一さんにお世話になって、SBIグループ・デジタルガレージグループ時代の話をしていただいて。後半は、今まさに起業家として挑戦中のナッジについての話をしていただきました。沖田さん、ありがとうございました。
沖田:ありがとうございました。